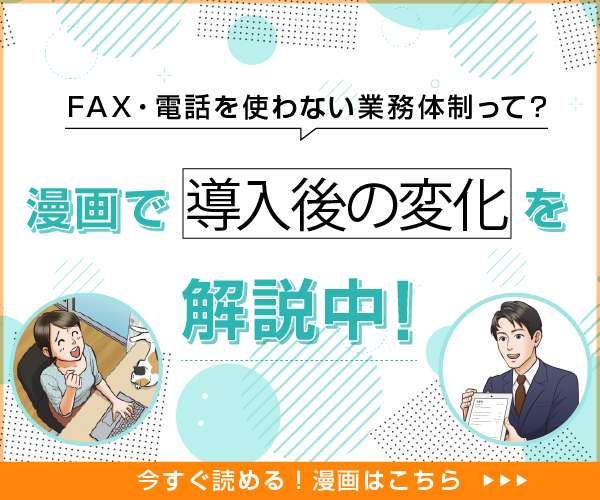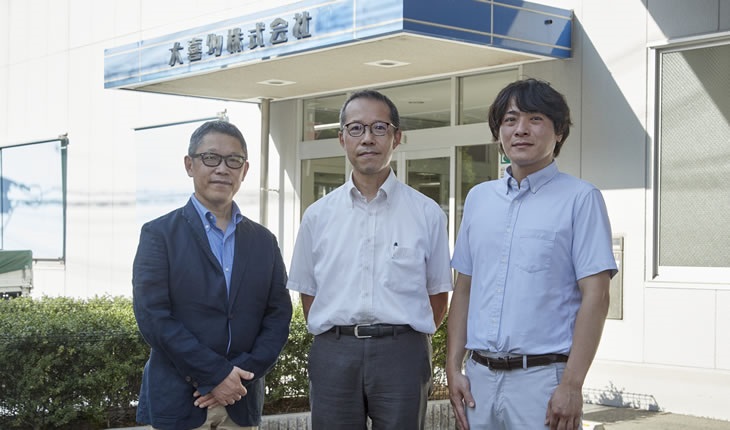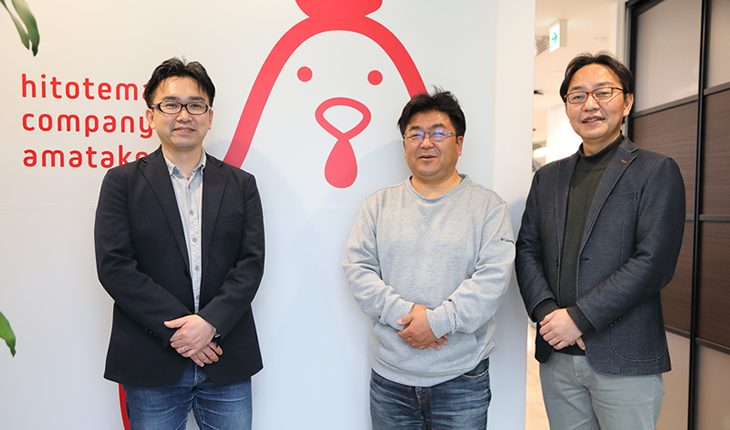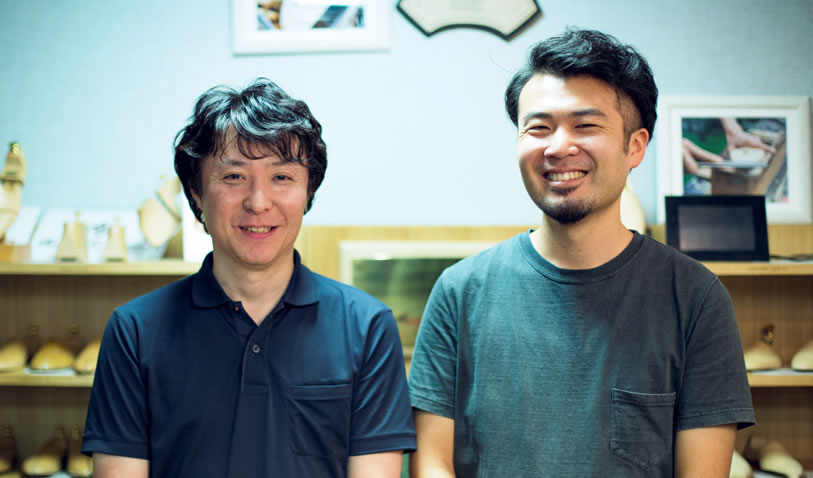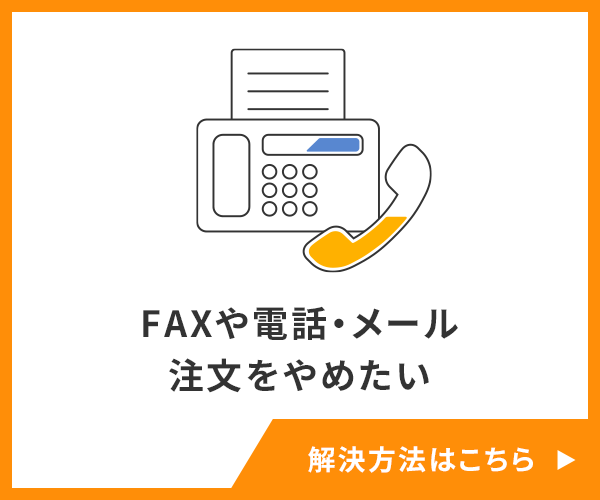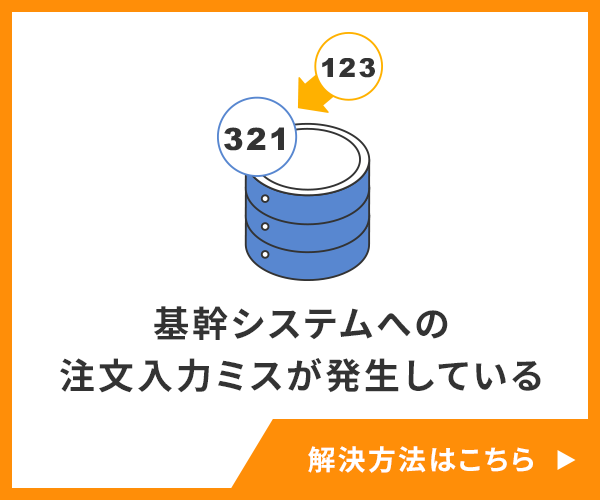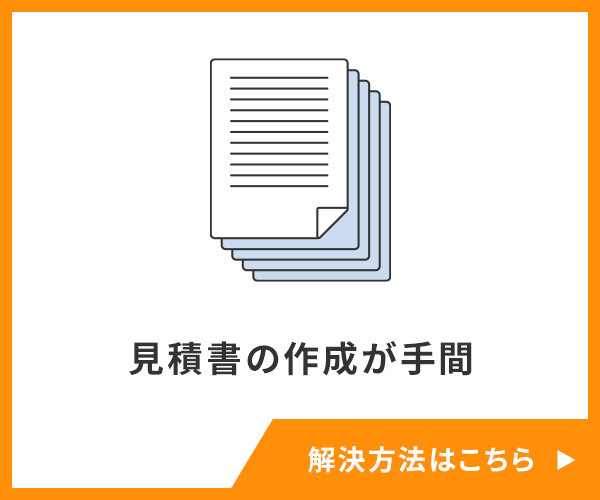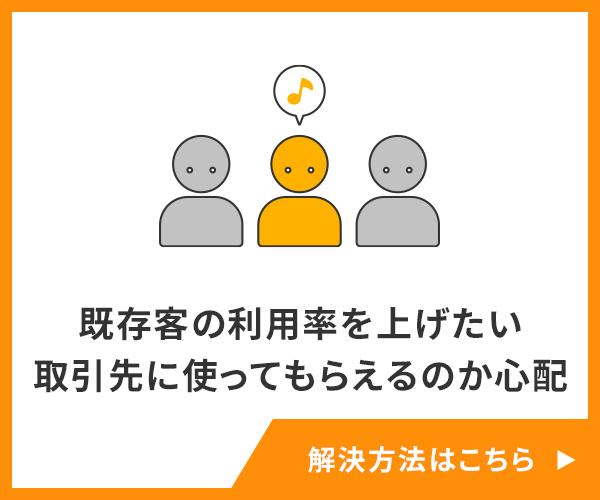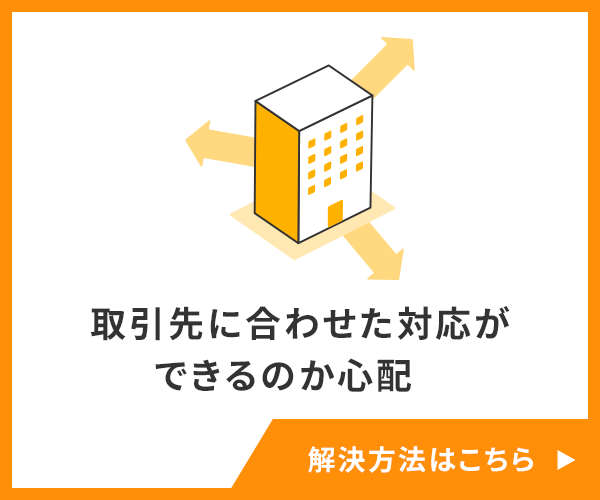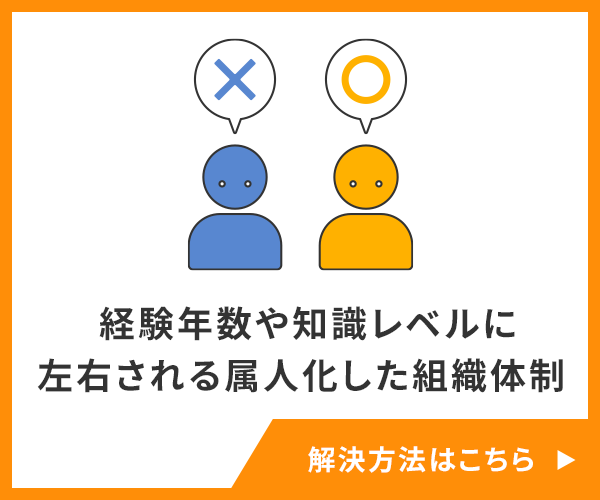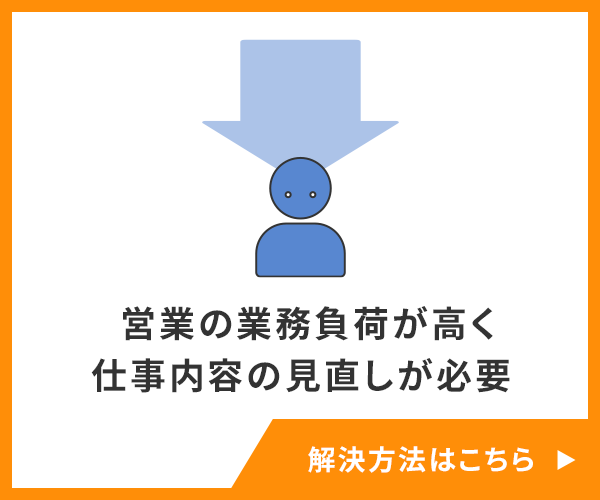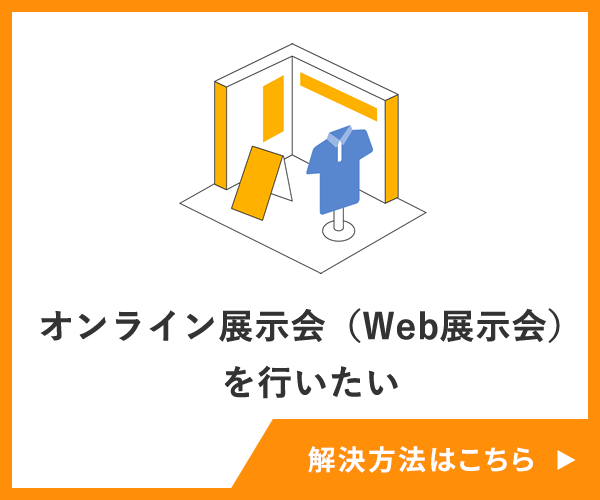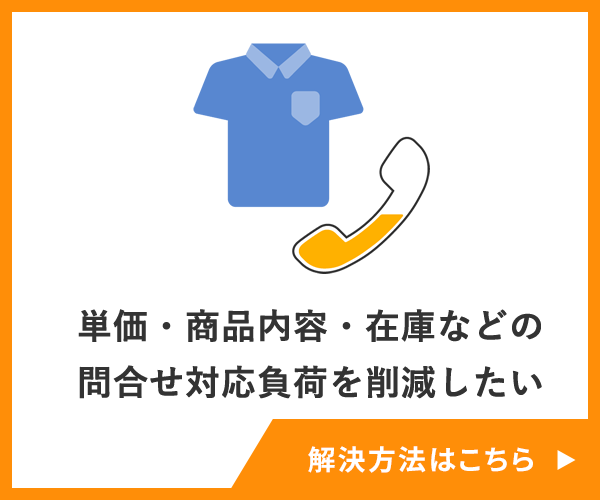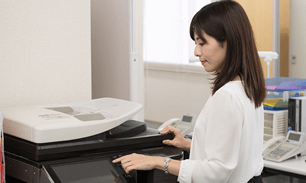お役立ち情報
Information
アイルが提供するお役立ち情報

注文書を電子化・データ化する方法とは?電子商取引への切り替えのススメ

企業間取引では注文書・発注書・見積書など多くの書類のやり取りが発生しますが、日本の企業間取引ではFAXでの注文が主流であり、読解ミスや抜け漏れの発生、仕分け作業などで業務負荷が増えています。
アナログでの取引は業務効率化の妨げになるため「注文書を電子化してデータで管理したい」と考えている企業は少なくありません。
今回は注文書を電子化するメリット・デメリットとは何か、スムーズかつ安全に電子化ができるおすすめの方法は何かまで、詳しく解説します。
目次
注文書の保管方法
従来は、注文書は紙で発行されたものをファイリングするなどして保管することが必要でした。しかし、1998年に成立した電子帳簿保存法により、注文書は電子データでの保存が可能となっています。
注文書を紙で保管する場合

注文書がFAXや郵送で送付されてくる場合は、そのまま保管をします。取引先からメールなどの電子データで送付されてくる発注書を紙で保管する場合は、印刷をする必要があります。
注文書の印刷などが終わったら、日付や帳票の種類、取引先ごとに注文書を整理します。いざという時にすぐ提示できるように、月別の保管が望ましいでしょう。
注文書を電子データで保管する場合
電子データ保管は、大きく分けて2つの方法があります。
スキャナ保存
FAXや郵送など紙の書類として送られてくる注文書も、スキャンやスマートフォンなどでの撮影、OCRでの読み込みなどさまざまな方法により、電子データ化して保管することができます。これらの保存方法は、一般に「スキャナ保存」と呼ばれます。
スキャナ保存の場合、2021年4月現在は、電子データ保管を開始する3ヶ月前までに所轄の税務署長へ提出して承認を得る必要があります。また、注文書の作成・受領後すぐにスキャンし、3日以内にタイムスタンプを押すなどの処理が必要です。
2022年1月1日に施行される電子帳簿保存法の法改正によって税務署の承認は廃止、タイムスタンプ期間が延長などの緩和は行われるものの、不備があった場合の罰則も強化されるため注意が必要です。
電子取引
メールにファイルを添付したり、EDIやBtoB ECサイトを通じて取引をしたりといったような形で、電子データとして送付された注文書は、そのまま電子データとして保管をします。これらの取引方法を総称して「電子取引」といいます。
メールやBtoB ECによる電子取引の場合、税務署への申請・承認は不要です。事前承認をすることなく、スピーディーに注文書の電子化へ移行することができます。
注文書電子化のメリット
注文書を電子化することで、保管の手間を削減できるだけでなく、さまざまなメリットが生まれます。ここでは代表的なメリットについて解説します。
コスト削減できる
注文書を電子化し紙でのやり取りをなくすことで、注文書の印刷や送付にかかるコストや手間が発生しなくなります。業務負荷の軽減により人的資源を有効活用でき、担当者の残業代など人件費の削減も期待できます。
注文書や事務所の数が多いほどこのようなコストはかさんでいくため、電子化すると長期的にはかなりのコスト削減につながるでしょう。
業務効率化できる
紙の注文書だとオフィスに行かなければ処理できなかったり、問合せや確認時に書類を探し出す手間がかかったり、データ入力しなければならなかったりと業務負担が大きくなります。電子化によりデータ検索などが可能になれば管理や運用が楽になるため、業務効率化に貢献します。
テレワークしやすい
注文書を電子化すれば、出社しなくてもシステム上での処理が可能になり場所や時間に縛られなくなるため、テレワークしやすくなります。
いつでもどこでも確認し作業できる環境を整えることで、リアルタイムで情報を共有して属人化を防ぐことも可能です。火事や地震といった災害による紛失リスクを避け、BCP対策や感染対策のテレワークにも対応できます。
環境保全に貢献できる

電子化によりペーパーレス化ができ、環境保全に貢献します。SDGsに取り組んでいる企業としてアピールすることも可能で、企業のイメージアップを図ったり採用ブランディングをしたりする際にもプラスに働きます。
経年劣化や汚損リスクがない
紙の発注書の場合、長期間保管しているとどうしても経年劣化により、印刷が薄くなったり紙が汚れたりして記載内容が確認しにくくなる恐れがあります。電子データは経年劣化の恐れがないため、長期間きれいな状態で保管できます。
セキュリティが強化できる
セキュリティ対策にも注文書の電子化が貢献します。紙だと書類の紛失リスクがあったり、担当者に管理業務が依存して管理が甘くなったり、管理方法によっては社内の誰でも見ることができますが、電子化すればデータ上で管理できるため紛失・盗難リスクが軽減し、管理の属人化も防げます。
注文書電子化のデメリット
一方で、注文書電子化にはデメリットもあります。ここでは気を付けるべきデメリットを解説します。
移行の手間がかかる
アナログからデジタルへ移行する際に作業フローが変わるため、抵抗感を持つ人も少なくありません。移行時には周知徹底の手間がかかりますが、アナログによる属人化は業務効率化の妨げになり、長期的には電子化したほうが業務負担を減らせることをきちんと伝えて啓蒙活動をしましょう。
データ化の手間がかかる
注文書を電子化する際、これまでFAXなどのアナログな手段で注文書のやり取りをしていた場合はデータ化の手間がかかります。さらにデータ化する際のルールも新しく制定・共有する必要があり、それなりの手間と時間がかかることを踏まえて電子化を進めたほうがいいでしょう。
書き込みできない
紙の注文書は確認事項などを直接書き込めますが、電子化すると書き込みができません。取引先と電話しながら注意点を書き込むといった手順は踏めなくなるため、補足事項は専用のエクセルに記入するなど別のやり方を考える必要があります。
情報漏洩のリスクがある
注文書電子化のメリットにセキュリティの強化がありますが、まったくリスクがないわけではありません。情報漏洩のリスクはあるため、データ化する際にセキュリティ面での不備がないかなど確認しながら進めてください。
注文書データ化の方法
それでは、どのように注文書をデータ化すればいいのでしょうか。注文書をデータ化する5つの方法について、それぞれのメリットとデメリットを踏まえて解説します。
自社内でPDF化する

一番シンプルな方法は、自社でスキャンしたり画像撮影したりしてPDF化することです。特にツールを導入する必要がなく、手軽に実施できることがメリットです。
デメリットは、すべて自社のマンパワーで行わなければならないため時間と手間がかかることです。今後も継続的に人員を割いて注文書を電子化しなければならず、業務効率化しにくいでしょう。初期の導入コストは抑えられるものの、長期的にはランニングコストがかかる方法だと言えます。
OCRソフトを利用する
OCRとは手書きの文字を自動でデジタル文字に変換する光学文字認識技術です。OCRソフトを活用することで、紙の注文書に書かれている文字をスキャンやカメラによって読み取り、自動でデータ化してデータ入力の手間を削減することが可能になります。
ただし、文字が雑に書かれている場合は正しく解読できない可能性があり、手慣れている得意先からの注文ほど認識ミスが起きる可能性が高まります。
読み違いからの誤注文が発生するリスクがあるにも関わらず、それでもコストはかかるので、コストパフォーマンスが高いかというと判断が難しいです。
外部委託する
データ化の作業を外部委託すれば、自社で対応する手間を削減しつつ、OCRソフトの読み取りミスといったリスクも回避できます。
一方で外注するため継続的にコストがかかる点がデメリットです。データ入力代行サービスは多々あり、相見積もりを取ることで最低限のコストに抑えることもできますが、個人情報の漏洩リスクがあったり低品質の納品を受ける可能性があったりと懸念点が残ります。
取引先に電子データで送ってもらう
取引先から注文票を受け取る際に、エクセルやPDFなどの電子データで送ってもらうことで注文書をデータ化する手間を軽減できます。
ただ、これは取引先次第のやり方なので、相手を説得する必要があり、自社でコントロールしにくいのが難点です。「A社はデータ化OKだがB社はNG」というように、取引先によってデータ化できないパターンもあり、管理が煩雑化するリスクがあるでしょう。
電子商取引に切り替える
電子商取引に切り替えて商取引そのものをデジタル化・システム化するのも、注文書をデータ化する1つの手です。
自社内でPDF化をしたりOCRソフトを利用したりする手間が不要となる上、取引先の負担も少なく、自社も取引先も注文書のやり取りが簡単にできるようになります。双方のメリットがあるので、スムーズに業務効率化ができるでしょう。
注文書を電子化するならBtoB向けECシステムがおすすめ

BtoB向けECシステムを活用することで、商取引そのものをデジタル化・システム化でき、注文書のデータ化がスムーズに行えます。BtoB向けECシステムは、企業間取引に必要な機能が標準搭載されていて、柔軟性が高く低コストで導入できる点が強みだと言えます。
BtoB向けECシステムにより注文書や見積書などの書類が不要になり、書類を読み取る業務を削減可能です。当然、紙の書類をデータ化したり保管したりする手間もかからず、大幅な業務効率化につながるでしょう。発注情報閲覧機能が標準装備されているので、仕入先でWebから発注情報を確認したり、その場でCSVデータ出力したりすることもできます。
ほかにも業務の標準化によって属人化を防ぎ、経験年数や知識レベルに関わらずだれでも注文書の処理ができるようにしたり、在宅勤務やテレワークが可能な環境にしてBCP対策をしたり、注文書以外にも見積書の作成や送付を効率化したり、請求業務を一括アウトソーシングしたりと幅広く活用できるのです。
BtoB向けECシステムを選定する際、費用対効果だけでなく信頼ができるシステム会社かどうかもチェックする必要があります。簡単に乗り換えできないため、倒産などのリスク回避も考えなければなりません。
「BtoB向けECのシステム会社を選定するうえで確認すべきポイント」は以下のリンクよりご確認ください。

30年以上BtoB専門のシステムを開発し続けているアイルのBtoB向けECシステム「アラジンEC」
アラジンECを開発しているアイルは30年以上BtoB企業専用のシステムを提供しており、その実績は約5,000社にものぼります。基幹システムのノウハウを活かしBtoB専用に開発したECであり、豊富な企業間取引のノウハウを活かして課題分析をしたうえで、企業に合った提案を行います。
業種や業界に合わせて柔軟にカスタマイズできる点も強みであり「基幹システムへの注文入力ミスを防ぎたい」「FAXや電話注文をやめたい」「見積書の作成を楽に行いたい」「テレワークできる環境に整えたい」などあらゆる課題を解決してきました。
たとえば、1,000店舗以上の取引先に食品を卸していた専門問屋では、FAX注文の伝票入力が深夜まで及んでいましたが、アラジンECを導入したことで伝票入力時間を最大約10時間も短縮し、3名以上の人件費とFAX用紙のコストを削減できました。受注対応における社員教育・確認・ミス対応などの手間が減り、格段に業務効率化できています。

8,000種類以上の商品を扱う首都圏最大級の総合食品商社では、月の明細行数が3万行もあり、発注を取りまとめる購買部では発注業務に加えて納品書や請求書の突き合わせ業務が負担となり、業務を圧迫していました。そこでアラジンECを導入したところ、業務量が約半分になり、年間3,000時間の効率化に成功しています。

各業界・業種ごとの商習慣を把握したうえで、各企業の課題を分析して提案できるのは「アラジンEC」ならではの強みです。導入後も「貴社専属チーム」がメンテナンスまでサポートするので、安心して導入・運用ができます。オンライン提案も行っているので、発注書のデータ化をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

松岡 憲二(マツオカ ケンジ)
ベンチャー系ECベンダーにてセールスプランナー、ECコンサルタント、事業責任者として十数年従事した後、株式会社アイルに入社。大規模ECサイトからASPカート利用のスタートアップサイトまで様々な種類のサイト構築を経験。BtoCとBtoB、両方のノウハウを併せ持つことが強み。
PICK UP
導入事例
導入されたお客様の具体的な課題や解決方法、導入後の成果など詳しくお話いただきました。
よくある課題
業種別
-

 アパレル・ファッション
アパレル・ファッション鞄(かばん)、靴(くつ)、スポーツ用品、
肌着、制服・ユニフォーム、靴下、帽子など -

 食品・飲料・
食品・飲料・
酒類食料品全般、業務用食品、製菓、飲料、酒、
ワイン、介護食品、調味料など -

 理美容品
理美容品ヘアケア、カラー剤、エステ器具、ネイル用品、
ボディケアなど -

 建築資材・
建築資材・
住宅設備床材、外装資材など
-

 日用品・
日用品・
介護用品衛生用品、生活雑貨
など -

 工業製品・
工業製品・
電子部品電子部品、機械製造
など -

 OAサプライ品
OAサプライ品文具、事務用品など
-

 医療機器
医療機器歯科機器、検査機など
-

 化粧品
化粧品コスメ、口紅、香水
など -

 インテリア・
インテリア・
家具照明、収納家具など
-

 スポーツ用品
スポーツ用品シューズ、ウェアなど
-

 アクセサリー
アクセサリーピアス、指輪など
-

 ブランド向け
ブランド向け
展示会オンライン展示会
システム

[受付時間]10:00〜12:00 / 13:00〜17:30(土日祝除く)
 お問合せフォーム
お問合せフォーム
お役立ち情報|BtoB EC・Web受発注システム「アラジンEC」
5000社以上のBtoBノウハウで企業間の受発注業務に特化した貴社専用のECを構築することが可能です。受発注業務の効率化・コスト削減・販売促進など様々なシーンでご利用いただけるBtoB ECサイト構築・Web受発注システムです。