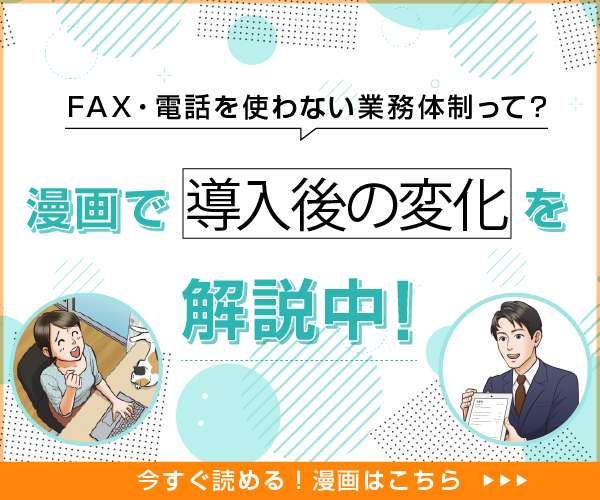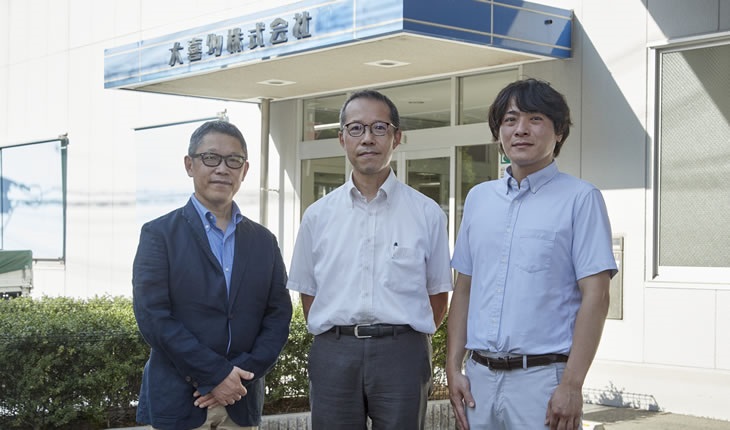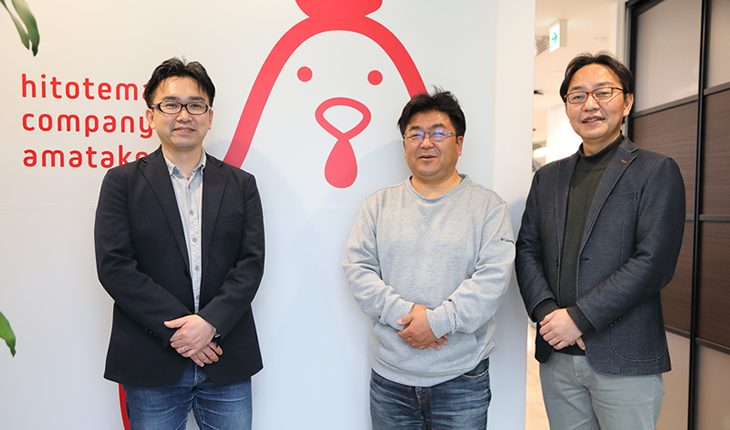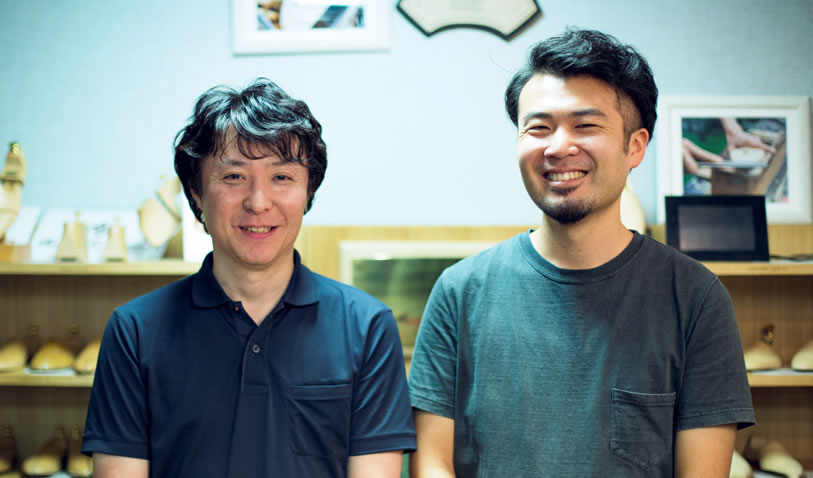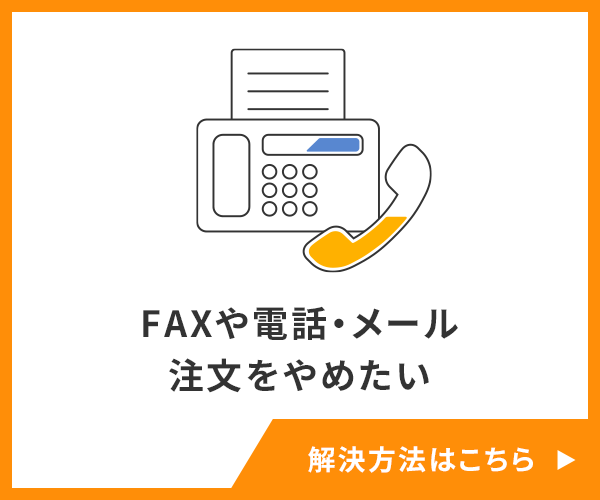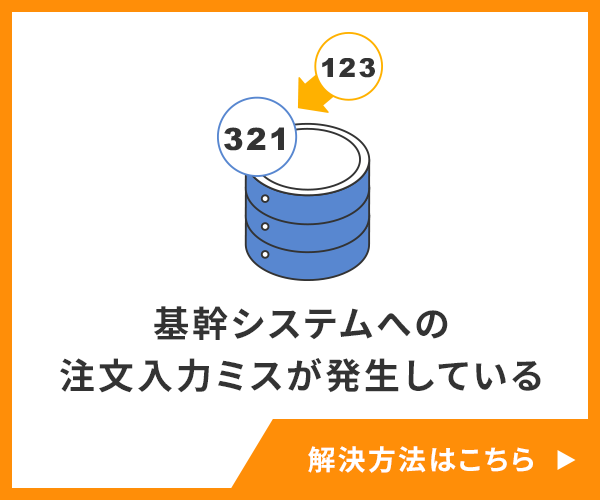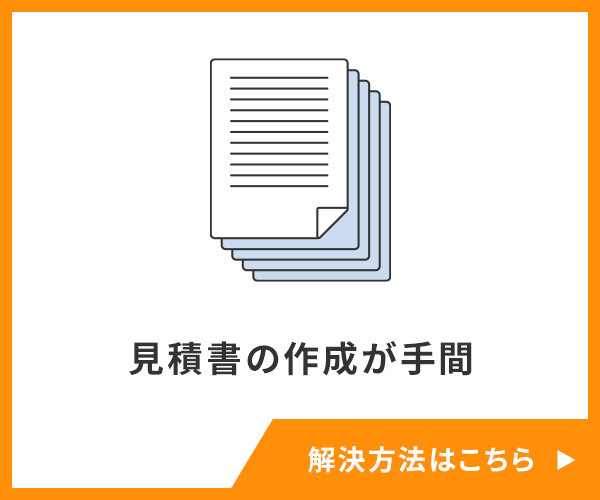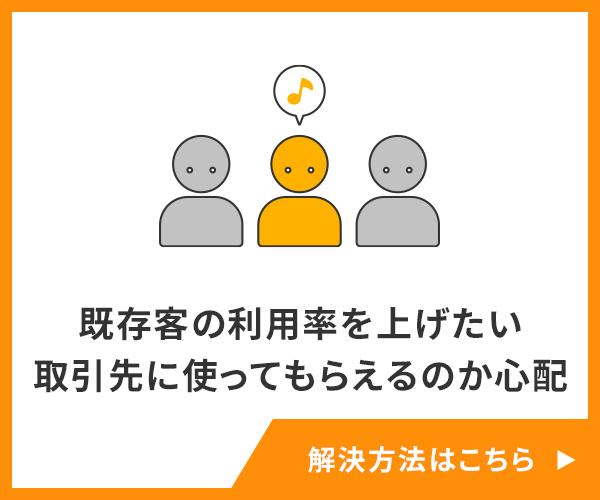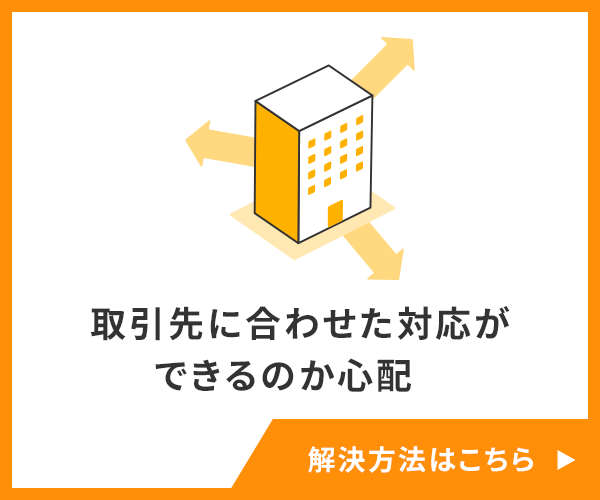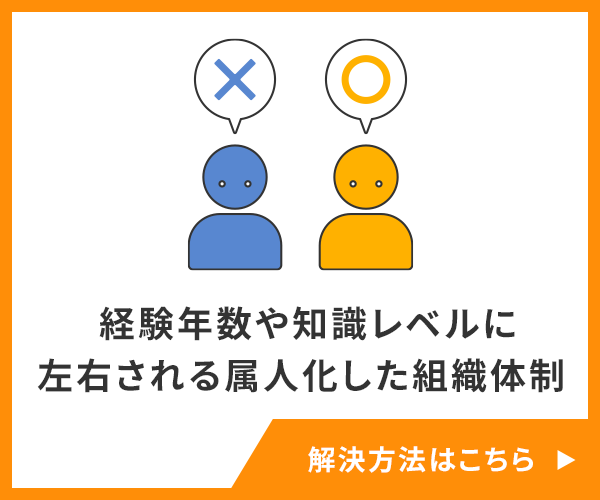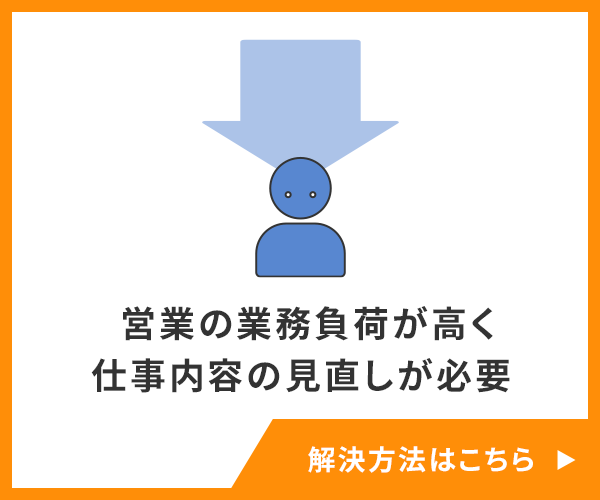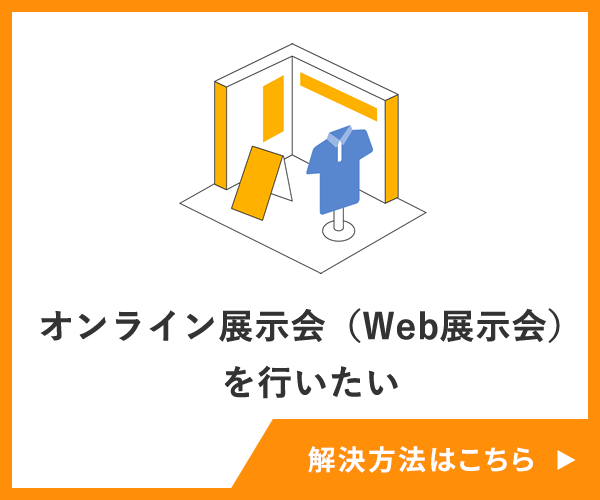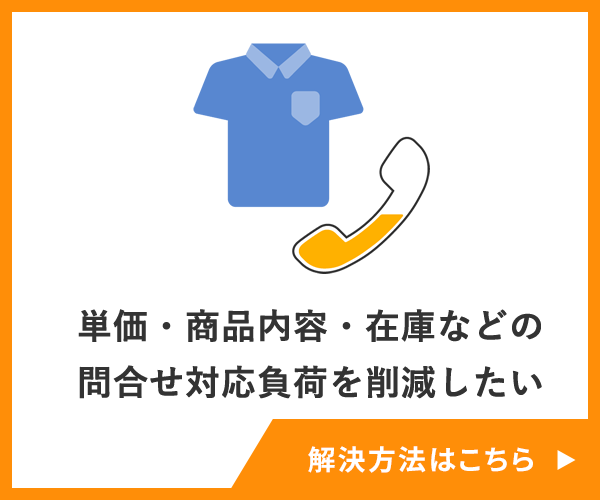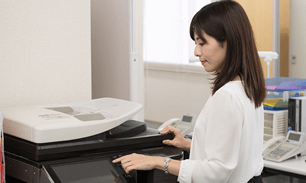お役立ち情報
Information
アイルが提供するお役立ち情報

企業間取引の問合せ対応削減にWeb受注システムをおすすめする理由

電話やメール、FAXなどで寄せられるお問合せへの対応に追われ、着手したかった業務に取り組めないまま定時を迎え、仕方なく残業……。そんな光景が常態化してはいないでしょうか?
企業間取引(BtoB取引)において、顧客からの問合せへの対応は毎日のように発生する「ルーティン業務」のように見えて、都度内容の異なる「イレギュラー業務」です。対応に時間を要するため通常業務の進行が止まるだけでなく、顧客対応にミスがあれば今後の取引に悪影響を及ぼすこともある重要な業務のひとつだといえます。
そこでこのコラムでは、企業間取引の問合せ対応削減について取り上げます。問合せ対応に関する課題や件数削減方法をご紹介し、問合せ削減に「Web受注システム(BtoB EC)の導入」をおすすめする理由を解説します。顧客からの問合せ対応に頭を悩ませている方や、Web受注システムの導入にご興味をお持ちの方はぜひ参考になさってください。
企業間取引における問合せ対応とは?
企業が受ける問合せの内容は、業種や業態によって大きく異なります。では企業間取引では、どのような問合せが寄せられるのでしょうか。
問合せ手段は「電話」「メール」が主流

顧客からの問合せの手段は、主に以下のチャネルです。
- 電話
- FAX
- メール
- LINEなどのSNSやチャットツール
- 問合せフォーム
電話やFAXで注文を受けている場合は、問合せも電話でくることが多いでしょう。メールやWebで注文を受けている場合は、メールや問合せフォームから問合せがくることもありますが、急ぎの場合はやはり電話での問合せが多くなる傾向にあります。
よくある問合せは「商品」「注文」に関する内容
企業間の商取引でよくある問合せは、やはり商品の注文に関する問合せです。注文の前後によく発生する問合せの内容は以下の通りです。
- 商品情報(スペックなど)の確認
- 納期・単価・在庫の確認
- 前回注文した内容の確認
- 取引条件(注文ロット数、単価、送料、支払い条件など)の確認
- 注文FAX・メールなどの到着確認
- 注文内容(数量・納品先など)の修正
- 出荷状況の確認
- 配送伝票番号の確認
問合せを受けた従業員は、すぐに分かることであればその場で回答できますが、商品の詳細上の確認や注文の不備調査などが必要な場合は、折り返し連絡で対応することになり、想定以上に手間と時間が掛かることもあります。
問合せ元は顧客だけではない
商品や発送に関する問合せは、顧客以外からも寄せられます。外出中の営業担当が、社内の基幹システムを確認できないため、商品スペックや在庫状況について電話で問合せをしてきたり、その他の部署から納期について問合せがきたりといった社内からの問合せも多く発生します。
部署間の関係性によっては最優先で対応しなければならないこともあり、社外からの問合せ同様にプレッシャーを感じることもあります。
問合せ対応がネガティブな影響を及ぼすことがある
電話が通じない状態が長く続いたり、問合せ対応者が焦るあまりに誤った情報を伝えてしまったり失礼な発言があったりした場合、注文内容や今後のお取引に悪影響を及ぼす恐れがあります。
こちらに落ち度がなくとも、先方の勘違いが発端でご不興を買う可能性もあるため、問合せを受けること自体がリスクだともいえます。
企業間取引の問合せ対応の頻出課題
ここでは、企業間取引の問合せ対応において発生することの多い課題・問題点をご紹介します。
- 問合せが集中すると他の受電ができなくなる
- 対応に時間がかかる
- 従業員に心理的負荷がかかる
問合せが集中すると他の受電ができなくなる

問合せや注文を電話で受けている場合、特定の時期・時間帯に電話が集中してしまうと電話回線が塞がってしまいます。それぞれの業界の繁忙期のほか、食品業界であればランチやディナーの営業後に在庫や納期の問合せが集中しやすいです。
顧客が問合せの電話をかけた際に通話中で電話がつながらない不通状態が長く続けば、顧客に迷惑をかけるだけでなく、クレームや顧客満足度の低下につながる恐れもあるため注意が必要です。
対応に時間がかかる
問合せへの対応は、想定以上に時間がかかるものです。過去に対応したことがある問合せ内容であればスムーズな回答が可能ですが、イレギュラーな対応や経験の浅い対応者の場合、必要な情報の検索やメール作成などの共有作業に時間がかかります。
対応中は通常業務ができない上、中断した業務を再開するのに時間を要することもあり、対応者にとっては大きなストレスになっていることもあります。
従業員に心理的負荷がかかる
先方が焦った状態で電話をかけてきたり、急ぎで対応しなければならない状況になったりすると、問合せ対応者の心理的負荷が高くなります。
特に、電話での問合せについては抵抗感を持つ従業員が多いです。若い世代の場合、家に電話機がなく電話を取ることに慣れていないケースも多く、「電話に出るのが怖い」と感じている方も多いと言われています。
常に架電があるコールセンターやカスタマーサポートの仕事とは違い、企業間取引の問合せはいつ電話がかかってくるか分からないことから、通常業務を行いながら待機すること自体が負担となることもあるようです。
問合せ対応は毎日発生するため、このようなストレスの積み重ねが離職の遠因となることもあります。
顧客からの問合せ件数削減の効果
問合せ件数を削減することによって、以下のような効果が期待できます。
- 業務時間の短縮
- 顧客満足度の向上
- 従業員の心理的な負担の解消
業務時間の短縮
問合せ件数を減らすことにより、これまで問合せ対応に充てていた時間の分だけ業務時間を短縮することができます。これにより、以下のような好影響が見込めます。
- 残業や休日出勤の削減
→ワークライフバランスの実現、従業員エンゲージメントの向上 - 新しい業務へのチャレンジ
→スキルアップ、売上増 - 他部署のヘルプ
→部門間連携の向上
顧客満足度の向上
企業間取引でよく発生する「商品の仕様・見積・納期・在庫などに関する問合せ」は、「顧客が知りたいことをすぐに確認できない状態」になっているために問合せが発生します。
問合せによって情報が確認ができたとしても、待ち時間は発生しますし、問合せをすることに対して「面倒だ」と感じていたり、「電話が苦手なので問合せをするのが憂うつ」と感じていたりするケースも考えられます。
「顧客が知りたいことをいつでも確認できる状態」を整え、問合せが発生すること自体を防ぐことで、顧客の利便性が向上し顧客満足度向上が期待できます。
従業員の心理的な負担の解消
問合せ対応は相手を待たせている状態のため、基本的には急ぐ必要があります。対応者の性格や立場、その時の状況によっては、問合せ対応業務が大きなストレスになりえます。効率化を無理に進めてしまうと、その負担が増大する恐れもあるでしょう。
問合せの発生件数を削減し、対応する頻度自体を少なくすることで、従業員の心理的負担の解消が見込めます。これにより離職防止・定着率向上にもつながるでしょう。
問合せ件数を削減する方法
問合せ対応の課題を解決するためには、問合せ件数を削減することが必要です。では、商品や注文、納期などに関する問合せを減らすためにはどのような対策を取れば良いのでしょうか。
ここでは問合せ件数の削減方法を、メリット・デメリットと共にご紹介します。
商品情報・注文情報を詳しく掲示する
商品の詳細に関する問合せを減らすためには、顧客が自身で商品情報を確認できる状態にすることが望ましいです。
商品カタログの冊子やデータ、新商品をPRするチラシなどに、サイズ・スペック・関連商品・配送リードタイムなどの情報を詳しく記載するほか、商品画像の数を増やすなどの方法があります。新規顧客が多い場合、支払い方法の解説を載せるのも有効です。
- 顧客の自己解決につながる
- テキストや写真の追加は少しずつ進められるので着手しやすい
- 写真や仕様を細かく掲載することでイメージがつきやすくなり、売上増も期待できる
- カタログの情報を増やしても顧客が注文時に見るとは限らない
- 取引先によって単価が異なる場合、参考上代しか記載できない
- 配送リードタイムは距離や在庫状況もあるため、目安しか表示できない
- (冊子カタログの場合)更新が半年や1年に一度になる
- (冊子カタログの場合)印刷・保管・処分にコストがかかる
- (冊子カタログの場合)必要な情報を探すのに手間がかかる
- (PDF等の電子カタログの場合)ダウンロード形式やデータ配布形式の場合、古いカタログを参照される可能性がある
FAQ(よくある質問)を作成・刷新する
カタログやWebサイトにFAQ(よくある質問)を掲載するのも一つの手です。問合せをせずとも、ユーザーがFAQページを見れば解決できるよう内容を充実させることで注文に関する問合せの数を減らすことが期待できます。
FAQの数を増やす、FAQページを検索しやすい仕組みにするなどの工夫も有効です。
- 顧客の自己解決につながる
- FAQの作成に時間と手間がかかる
- ユーザーがFAQを都度見るとは限らない
AIを活用して問合せ対応を自動化する
近年話題のAIも、問合せ削減に活用することができます。AIチャットボットで自動返答する仕組みを導入する、AIでFAQを構築する、などの方法があります。
- 顧客の自己解決につながる
- 手間をかけずに問合せ削減ができる
- AIに関する知見を持った人員が必要
- 特有の商習慣がある場合、柔軟に対応できるように調整が必要
- AIチャットボットの精度が低い場合、適切な回答ができずトラブルやクレームにつながることもある
業務をデジタル化する
問合せの発生を根本的に解決するためには、業務のデジタル化がおすすめです。具体的には、デジタル化により以下のような仕組みを構築することで、問合せ件数の削減を図ることができます。
【1】いつでもどこでもWebにて閲覧可能な仕組みを構築
業務プロセスをデジタル化し、ユーザーが以下のような情報を常に確認できる状態にすれば、問合せを減らすことができます。
- 注文が可能かどうか(在庫があるかどうか)
- どんな商品なのか(商品詳細説明や画像)
- 最短でいつ届くのか(配送リードタイム)
- 過去の注文履歴(以前頼んだ商品の内容)
- 取引条件(支払条件・保障内容・キャンセルポリシーなど)
【2】受注システムから自動的にメール配信通知する仕組みを構築
社内の業務システムのステータス情報が更新されたタイミングで、以下のような情報を顧客にメール配信する仕組みを構築することで、顧客は情報を把握することが可能となり問合せを減らすことができます。
- 納期情報
- 出荷状況
- 配送伝票番号
受注業務に関する問合せ削減なら「Web受注システム」
Web受注システム(BtoB EC)で受注業務をデジタル化することで、受注業務を効率化するだけでなく問合せ対応を減らすこともできます。
Web受注システム(BtoB EC)とは?
Web受注システム(BtoB EC)とは、企業間の商取引をWebで行うシステムです。オンラインで顧客からの注文を受けることにより、受注業務にかける時間を大幅に削減し、顧客の利便性を向上することができます。
Web受注システムについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

Web受注システム導入のメリット
Web受注システム導入のメリットは、受注業務の削減や顧客の利便性向上だけではありません。導入企業にとっても顧客にとっても、多くのメリットがあります。
- 受注業務のミス・工数削減
- 各種問合せ対応削減
- 既存顧客からの受注アップ
- 新規顧客の開拓
- 他社との差別化
- 商品詳細情報を迅速に確認可能
- 商品発注業務の利便性向上
- EC利用限定の特典享受
以下の記事では、上記のメリット各項目について詳しく解説しています。

Web受注システム導入の注意点
取引年数や業種・業態によっては、電話やFAXなどでのアナログな発注からWeb受注システムでの発注への移行に抵抗感を示す顧客が多いこともあります。アナログな注文チャネルをなくして完全にデジタル化することは難しいといえるでしょう。
ただし顧客のうちの一部でもデジタル移行することができれば、問合せ件数の削減にはつながります。
問合せ削減にWeb受注システムをおすすめする3つの理由
ここでは、なぜ問合せ削減にWeb受注システムの導入をおすすめするのか、その理由をご説明します。
在庫・納期・商品詳細などのよくある問合せが減る

顧客が注文する際、問合せをせずとも「注文可能かどうか」「いつ届くのか」などの情報をWeb上で確認することができます。不明点を顧客が自己解決できるため、商品の在庫や納期に関する問合せの発生が大幅に減ることが期待できます。
Web受注システムの商品ページに情報を載せれば、注文時に確認してもらいやすいため商品詳細についての問合せ削減にも効果的です。紙やPDFのカタログとは異なり、注文をする際に必ず開くページのため、閲覧率が高まります。
受注ミスへの問合せが減る
電話やFAX、メールでの受注は聞き間違いや読み間違い、コピペミスといった受注時の人的ミスが発生します。Web受注システム経由で受注できるようになれば、このような人的ミスの件数も減るため、「注文内容が間違っている」といった問合せの発生件数が減ります。
業務の標準化・平準化が実現する
問合せ対応をスムーズに行うためには、対応経験と製品知識が必要です。対応者の経験・知識に差がある場合、対応品質にムラが出たり、対応できる人に業務が偏ったりすることがあります。Web受注システムの活用が進めば、このような業務の偏りも少なくなります。
Web受注システムで問合せ削減に成功した事例
Web上で受注業務を行えるWeb受注システム・BtoB EC「アラジンEC」の導入によって、問合せ削減などの問合せ業務改善に成功した企業の事例をご紹介します。
【問合せ削減事例・1】電話対応件数を大幅削減!売上アップも実現

まず、Web受注システムの入替え(リプレイス)によって問合せ業務の大幅な改善に成功した事例をご紹介します。
サントリーマーケティング&コマース様は40年以上の長きにわたり、酒販店や飲食店向けにグラスやラッピング用品・販促品などを販売しています。アラジンECの導入前もWebで注文できるサイトは持っていましたが、商品情報は冊子カタログで展開していたため顧客からの電話問合せが多く、問合せ対応業務の負荷が高くなっていることが課題となっていました。また、タイムリーな販促ができないことや、新規顧客の獲得ができないことも事業成長における課題点でした。
上記のような課題を解決するため、同社は2016年にアラジンECを導入。これまで問合せが多く寄せられていた「商品のサイズ・形状」「酒の種類とグラスの相性」などの情報を商品ページに詳しく記載すると共に、商品検索時にカテゴリ・価格・容量・素材などさまざまな条件で絞り込みができるような仕組みを整えました。顧客自身が必要なタイミングで必要な情報を確認できる状態にしたことで、電話対応件数は年間で8,000件もの削減を達成。また、既存顧客のアップセルや新規顧客の獲得などにより、Web受注の売上は前年比187%、Web受注件数は同178%と大幅アップしました。

【問合せ削減事例・2】ランチ後の注文集中からの解放!注文の自動制御でストレスフリーに

中華麺の製造・販売をされている瑞穂食品工業様は、「麺屋棣鄂(ていがく)」の屋号で知られ全国から注文が寄せられる老舗製麺所です。
同社は顧客の多くがラーメン店ということもあり、ランチの営業時間後に注文が集中しやすいことが大きな課題となっていました。電話注文が集中する昼過ぎの時間帯になると電話回線が埋まってしまい、問合せ電話がつながらない状態になっていたのです。
そこで同業他社から紹介を受け、「アラジンEC」を2021年に導入。受注業務のデジタル化を図り、受注・問合せ業務の負荷軽減を実現しました。また、商品の注文や配送に関して細かなルールがあり判断が属人化していましたが、これらのルールをシステムに登録したことで注文時の自動制御が可能に。これにより注文の確認や修正の連絡が不要となりました。注文に関わるミスや確認作業がなくなったことで、同社も顧客も利便性が向上しストレスフリーになったといいます。

「アラジンEC」で問合せ・受注業務のDXを!
問合せ対応業務は、受注業務をデジタル化することにより大幅な改善・削減が見込めます。卸売業や小売業の企業様が受注業務のデジタル化に踏み切るのなら、Web受注システム(BtoB EC)「アラジンEC」の導入をおすすめします。
「アラジンEC」以外のWeb受注システム(BtoB EC)は、BtoC向けのECシステムをBtoB向けにカスタマイズしたものが一般的です。しかし、「アラジンEC」はBtoB企業向けに開発されたWeb受注システム(BtoB EC)のため、企業間取引特有の商習慣への対応が可能です。顧客や納品先ごとに単価や送料を個別設定したり、バラ・ボール・ケースなど販売荷姿別での制御が可能なため、注文や発送に関する問合せ件数の削減が期待できます。
企業間取引に役立つ豊富な機能については、以下のページにてご確認いただけます。

問合せ対応業務の所要時間やストレスは、マネジメント層が想定している以上に負荷が高いものです。問合せ対応を減らすことにより、業務時間の短縮に大きな効果をもたらします。
業務時間が短くなることにより、従業員が利益創出につながる業務に時間を充てたり、プライベート面を充実させたりすることができるようになりモチベーション向上につながります。管理職がマネジメント業務に専念できるようになるといった良い変化も期待できます。
Web受注システムで顧客自身が不明点を自己解決できる仕組みを整えることで、問合せの発生がなくなるだけでなく顧客の利便性も向上します。
問合せ業務と受注業務の改善が同時にできる「アラジンEC」の導入で、三方よしの問合せ対応DXを実現しましょう。

松岡 憲二(マツオカ ケンジ)
ベンチャー系ECベンダーにてセールスプランナー、ECコンサルタント、事業責任者として十数年従事した後、株式会社アイルに入社。大規模ECサイトからASPカート利用のスタートアップサイトまで様々な種類のサイト構築を経験。BtoCとBtoB、両方のノウハウを併せ持つことが強み。
PICK UP
導入事例
導入されたお客様の具体的な課題や解決方法、導入後の成果など詳しくお話いただきました。
よくある課題
業種別
-

 アパレル・ファッション
アパレル・ファッション鞄(かばん)、靴(くつ)、スポーツ用品、
肌着、制服・ユニフォーム、靴下、帽子など -

 食品・飲料・
食品・飲料・
酒類食料品全般、業務用食品、製菓、飲料、酒、
ワイン、介護食品、調味料など -

 理美容品
理美容品ヘアケア、カラー剤、エステ器具、ネイル用品、
ボディケアなど -

 建築資材・
建築資材・
住宅設備床材、外装資材など
-

 日用品・
日用品・
介護用品衛生用品、生活雑貨
など -

 工業製品・
工業製品・
電子部品電子部品、機械製造
など -

 OAサプライ品
OAサプライ品文具、事務用品など
-

 医療機器
医療機器歯科機器、検査機など
-

 化粧品
化粧品コスメ、口紅、香水
など -

 インテリア・
インテリア・
家具照明、収納家具など
-

 スポーツ用品
スポーツ用品シューズ、ウェアなど
-

 アクセサリー
アクセサリーピアス、指輪など
-

 ブランド向け
ブランド向け
展示会オンライン展示会
システム

[受付時間]10:00〜12:00 / 13:00〜17:30(土日祝除く)
 お問合せフォーム
お問合せフォーム
お役立ち情報|BtoB EC・Web受発注システム「アラジンEC」
5000社以上のBtoBノウハウで企業間の受発注業務に特化した貴社専用のECを構築することが可能です。受発注業務の効率化・コスト削減・販売促進など様々なシーンでご利用いただけるBtoB EC・Web受発注システムです。