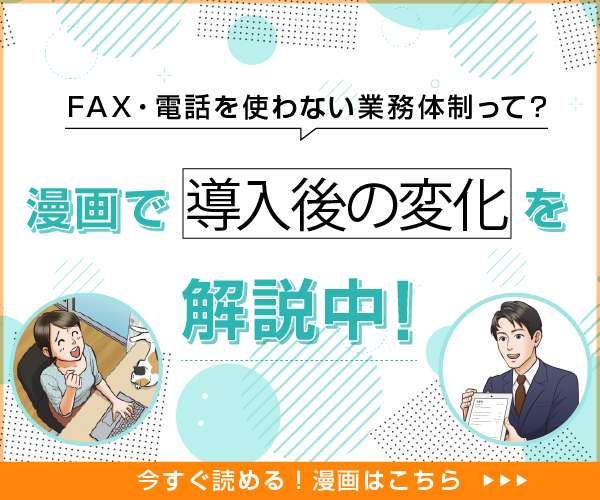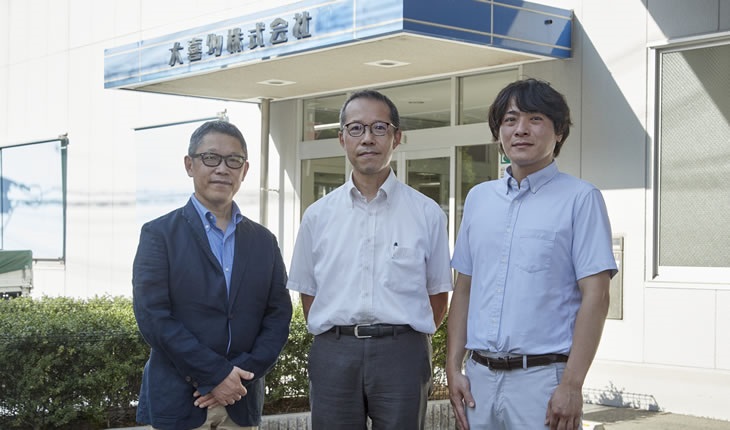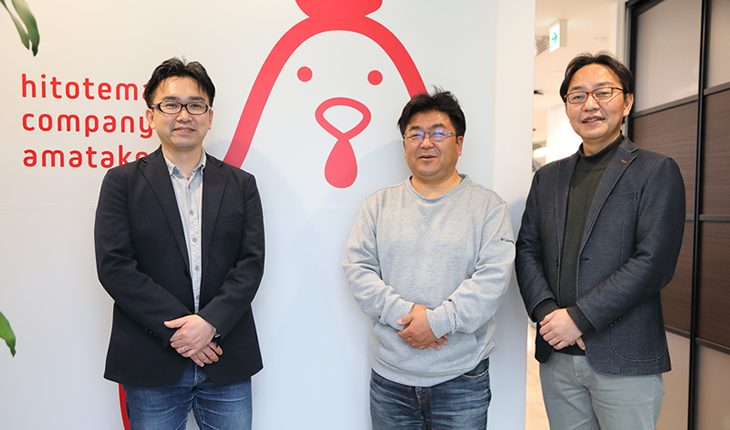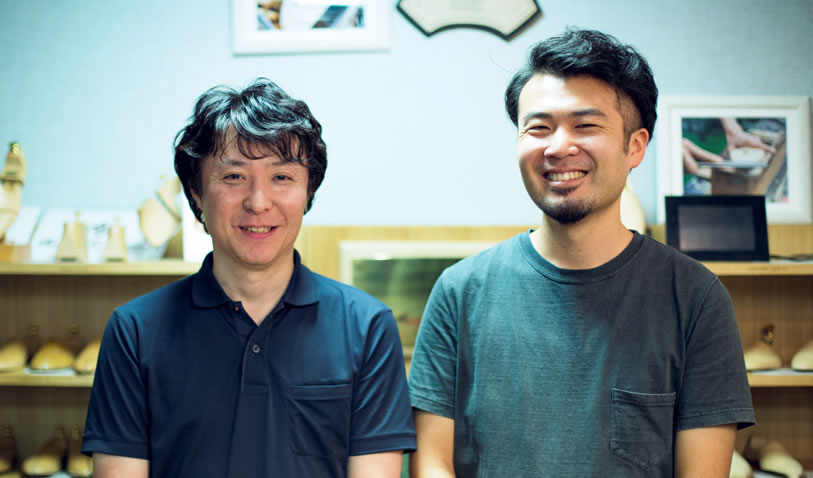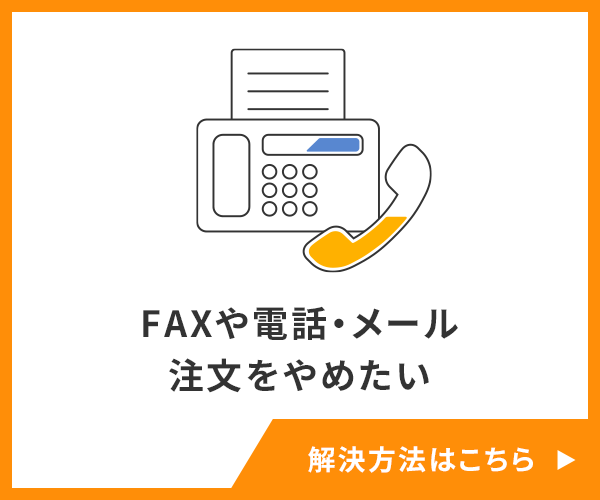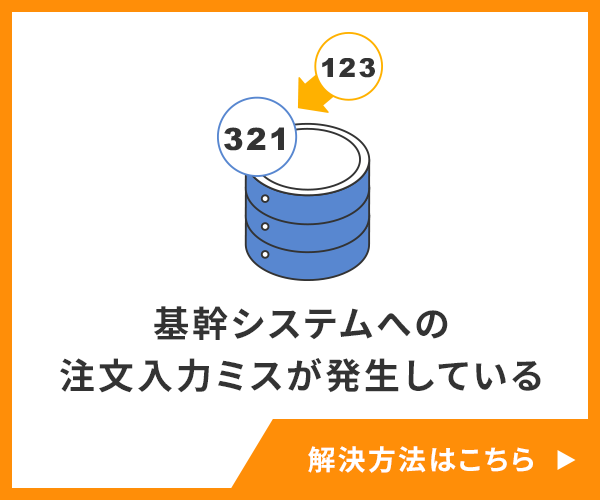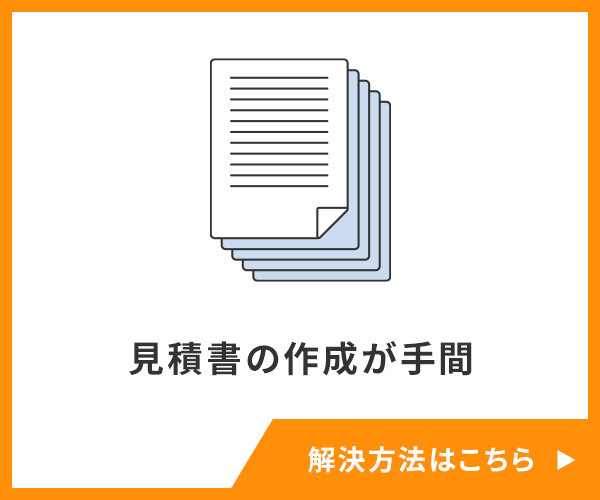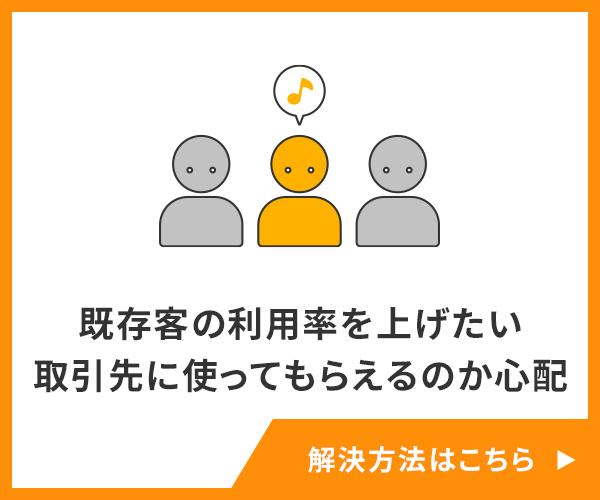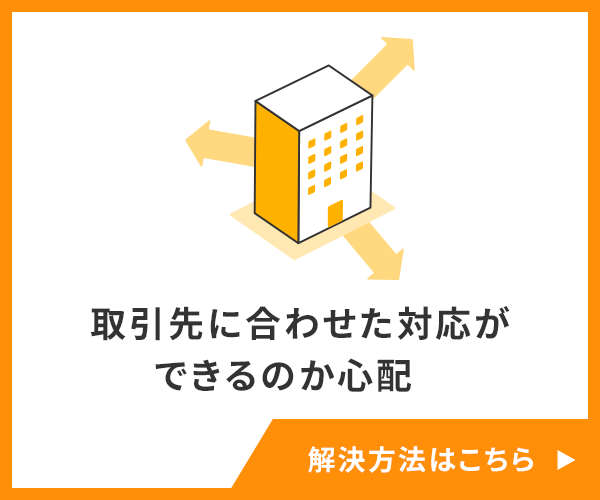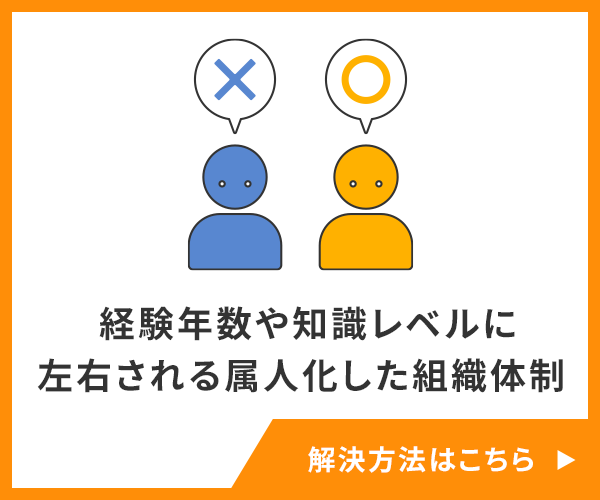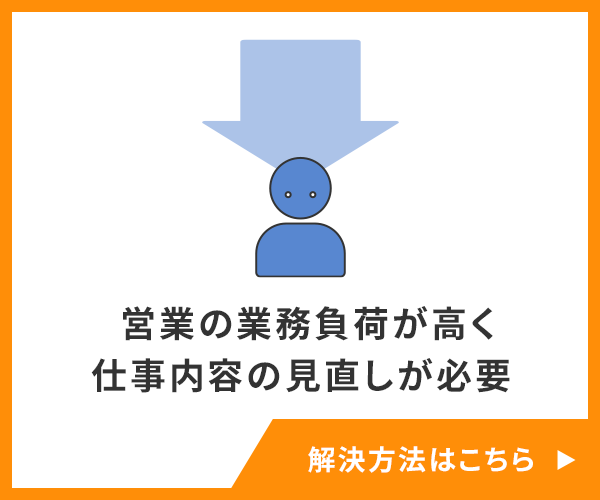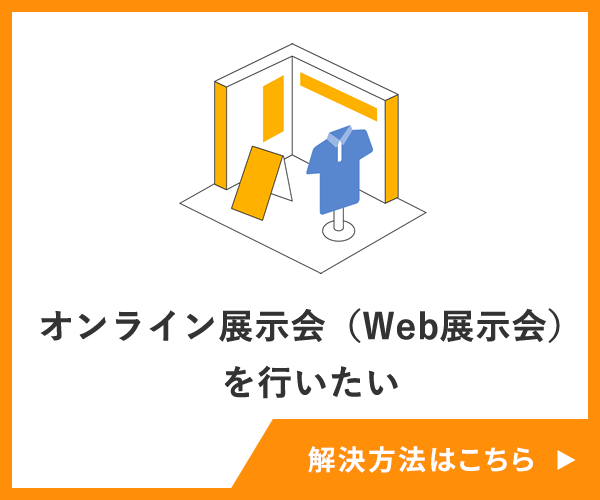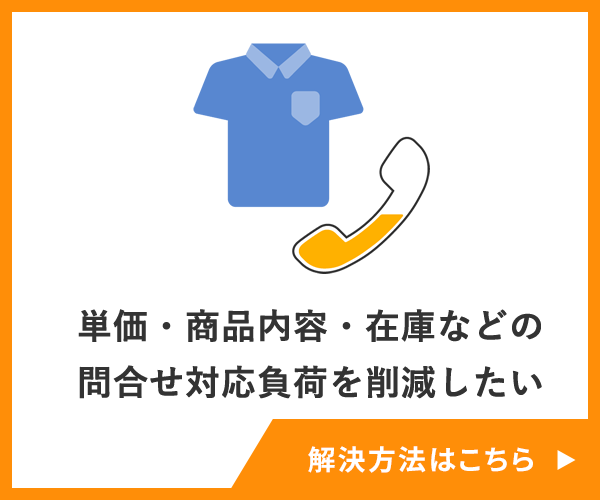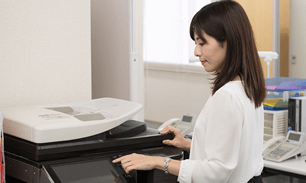お役立ち情報
Information
アイルが提供するお役立ち情報

ルート営業を驚くほど効率化できるBtoB ECサイトの魅力とは

BtoBビジネス、企業間取引においてルート営業は必要不可欠です。ルート営業の本質は既存の得意先との関係性を維持し、強化することでしょう。得意先を訪問してコミュニケーションを重ねることで、継続的に発注してもらうことが目的です。
コロナ禍になり対面営業がしにくくなったことから非対面営業がクローズアップされがちですが、ルート営業そのものは継続する必要があります。これからの時代、非対面でもルート営業を効率的に行うために欠かせないのがBtoB ECサイトです。
そこで今回は、BtoB ECサイトの解説も含め、ルート営業を効率化する方法について詳しくご紹介します。
目次
ルート営業を効率化すべき理由
まず、なぜルート営業を効率化するべきなのか、その理由について改めて考えていきましょう。
コロナ禍で対面営業が難しくなったから

コロナ禍で対面コミュニケーションが取りにくくなり、頻繁に取引先へ直接赴いて商談することが困難になりました。もはや非対面営業が常識になりつつあります。
今後コロナが収束したとしても、コロナ以前の社会には戻れないといわれています。これまでのやり方から脱却するとともに、対面営業以外の方法でルート営業を効率化することが求められます。

頻回・長時間の訪問が難しくなったから
コロナ禍により、頻繁な訪問や長時間の訪問は特に歓迎されなくなったため、こまめな対面営業によるアプローチは避けざるを得ません。訪問営業を最小限にする必要があります。
頻繁な訪問や長時間の商談をしなくても、これまでのように取引先からの発注を促進できるルート営業の方法に切り替えるべきでしょう。
新規営業よりも発注頻度が高く、無駄が生まれやすいから
ルート営業は取引先からのリピート注文を促進するものなので、ハードルが高い新規営業よりも発注頻度が高い傾向があります。発注のたびに在庫の確認や見積書の発行、注文書の回収などをする必要があり、自然と事務作業も多くなりがちです。
ルート営業に付随する作業を効率化しないと、本来の営業活動に専念できないだけでなく、事務作業のために残業や休日出勤をする必要も出てきてしまいます。このような状況が続けば営業担当者の労力と残業時間ばかりがかさみ、時間外労働によって人件費も増えていきます。
営業が「ルート営業がきつい」と感じる理由
非効率なルート営業を「きつい」と感じる営業担当者は多いですが、既存顧客とは関係性ができているため新規営業よりも楽なイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。マネジメント層の方の中には「なぜルート営業なのにこんなに残業しているのか?」「ルート営業の離職率が高いのはなぜ?」と疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
ここではルート営業の担当者が「ルート営業がきつい」と感じる理由を解説します。
頻繁な訪問による労力がかかる
ルート営業は関係性維持のためにも頻繁なコミュニケーションが求められるため、取引先に足を運ぶ回数も多くなりがちです。天候に関わらず移動する労力や時間、交通費などのコストも発生し、それが負担になって「ルート営業がきつい」と感じる営業担当者もいます。
効率化しようと思っても、今まで訪問していた回数を急に減らすとマイナスイメージを与えかねないため慎重になり、必要性が高くなくても惰性で足を運び続けるケースもあります。
得意先の無茶な要望を断りにくい
取引先と親しくなるほど要望をぶつけられる回数も増え、営業は難しい対応を迫られるものです。ルート営業を長く続けている得意先から「これだけ取引しているんだからもっと割引してよ」などと無茶な要望を言われると、無下に断るわけにもいかず、会社と取引先の板挟みになることもあるでしょう。
そこでうまく取引先を満足させる対応ができないと、その後の発注が減るなど売上が下がることもあります。そうすると会社から「どうして売上が落ちているんだ」と指摘され、ストレスを感じる営業が多いです。
仕事が単調になりやすい

今までの取引が長いほど、取引の内容が固定化して新しい提案が受け入れられにくくなります。必然的にルート営業の仕事内容も固まっていき、仕事が単調になってつまらなく感じてしまう人も少なくありません。
安定したルーティンワークが得意な人であればさほどストレスにはなりませんが、日々変化を感じて成長したい人からすると、やりがいを見いだしにくくなることもあるのです。モチベーションが低下した結果、作業効率が落ち労働時間が無駄に伸びている可能性もあります。
売上を伸ばしにくい
ルート営業は既存顧客にアプローチするので発注のハードルが低いように感じますが、今まで通りの売上は立てやすくても今まで以上の売上は立てにくいことが特徴です。新しい商品を紹介してアップセルを狙っても、なかなか受け入れられないでしょう。
ルート営業であってもノルマを課されるケースもあり、これまで以上の売上をノルマ設定されると達成するのは困難です。関係性ができているからこそ、取引先も遠慮なく「それはいらないよ」と断れますし、営業も「変に押し売りして関係性を壊したくない」という恐れから強くアプローチできないケースもままあります。
ルート営業を効率化する「BtoB EC」のメリットとは?
では、どうすればルート営業を無理なく効率化して、売上アップを目指せるのでしょうか。その解決方法の1つが、企業間取引をオンラインで行う「BtoB EC」です。BtoB ECを活用することで、非対面営業はもちろん、対面営業も効率化できます。
国内のEC市場は年々拡大していて、経済産業省が2020年5月に発表した「令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)」によれば、2019年のBtoB EC市場規模は、2018年から2.5%増の352兆9620億円でした。BtoCの約18倍の金額が動いており、今後も伸びていくと思われます。
ここでは、営業担当者がルート営業でBtoB ECを活用するメリットを解説します。
BtoB ECとは何かを詳しく知りたい方はこちら!

出先で過去の注文を確認し、ニーズに合った提案ができる
過去の情報だけでなく直近の取引も含め得意先の情報をしっかり把握せず、営業先に赴いた場合「この間、うちが注文した商品は何だっけ?」と聞かれてもその場で答えることができず、信頼を損なうリスクがあります。ルート営業のたびに最新情報を頭に入れておかないと、取引先に合わせた提案がしにくいでしょう。
ECサイトはタブレットやスマホでも閲覧できるので、営業担当者が訪問前に自身の端末を使用して、得意先の過去注文日や注文商品を確認することができます。過去の注文内容を踏まえ、リピート注文を促したり、ニーズに合った関連商品を案内したりすることで、売上アップを目指せるでしょう。
またECサイトであれば関連商品が自動表示されるケースもあり、営業担当者自身が思いつかない関連商品もおすすめしやすくなります。事前に設定しておけば、得意先別に商品の出し分けをすることも可能で、案内ミスを防げる点もメリットです。

新商品や関連商品の画面を見せながら提案できる

ルート営業で新商品やキャンペーンを紹介したくても、手元に資料がなく「追って郵送します」「戻り次第メールでお送りします」と言って、後から提案することも多いでしょう。無事発注につながるケースもありますが、機会損失になってしまうリスクもあります。その場で提案したほうが、熱量が高い状態で説明ができ、成約率が上がるでしょう。
こうした時、デジタルカタログとしても活用できるBtoB ECサイトが活躍します。これまで個別で印刷して手渡ししていた販促資料や新商品カタログを持参していなくても、得意先でタブレットやノートパソコンを開いてECサイトを見せることで、おすすめの商品を提案できます。重くて分厚い商品カタログを毎回持ち歩く必要がなくなり、営業担当者のストレスも減るでしょう。
在庫や単価の確認、見積発行、注文などに即時対応できる
ルート営業の訪問時に取引先から商品の在庫状況や単価について確認されたら、オフィスに確認の電話をしたり持ち帰って確認したりすることが多いのではないでしょうか。BtoB EC サイトであれば、その場で即時確認して回答することができます。
さらにECサイトに見積発行機能がついていれば、意外と時間がかかる見積発行にも即時対応可能です。タブレットやノートパソコンを取引先と一緒に閲覧しながら、得意先が指定する商品をカートに投入することで、すぐに見積書を作成できます。BtoB ECの機能にもよりますが、見積書は得意先がPDFにて保管し、必要に応じて印刷することも可能です。
もちろん、ECサイトではその場で注文できるので、ルート営業中に発注を確定させることもできます。画面を見ながら商品をカートに投入して注文確定ボタンを押せば、控えとして注文確認メールが得意先担当者と営業担当者に送信され、伝票を起こす必要もありません。機会損失のリスクが減るでしょう。

リモート営業ツールとして活用できる
電話やZoomなどのWeb会議ツールとBtoB ECサイトを併用することによって、直接訪問することなく営業活動することも可能です。出張を伴う営業活動の頻度を下げることも可能ですし、天候や交通事情の都合でこれまで訪問が出来なかった状況でも対応が可能です。当然、移動に伴う時間の短縮や、交通費などの経費削減にも繋がります。

得意先のEC利用率と顧客満足度を上げられる

当然ながら、取引先がECサイトを利用しなければBtoB ECの恩恵は受けられません。BtoB ECを導入する際、最大の懸念点は「これまでアナログで受発注してきた取引先がECサイトを利用してくれるかどうか不安」というものですが、ルート営業により不安を払しょくできます。営業担当者が取引先に行う啓蒙活動こそ、最も有効なEC利用促進の手段だからです。
ルート営業の訪問時に得意先と一緒に会員登録を行うことで、ECサイトの登録率は格段に上がります。これまで紹介したようなEC活用法を、実際に画面を見ながら紹介し体感いただくことで、取引先もECサイトの利便性を理解し、日々の細かな発注は自らECサイトで行うようになります。ECサイトを活用すれば、場所や時間を選ばずに在庫状況や価格、商品スペックなどを確認して発注できるようになり、自然と顧客満足度も上がっていくでしょう。それがルート営業の効率化に直結します。
営業担当者のモチベーションになる
ECサイト経由での発注に対しても、その取引先の営業担当者のポイントとなるように評価制度を見直すことで、営業担当者のモチベーション維持につながります。対面営業での直接的なセールストークが苦手な営業担当者でも、ECサイト経由のマイルドなアプローチであれば抵抗なくできるケースもあり、さらなる売上アップが期待できます。
また、細かな在庫確認や価格確認、見積発行などの事務作業も効率化され負担が軽減されることで、営業担当者が営業活動に集中しやすい仕組み作りにつながります。BtoB ECの導入でなるべく営業担当者の負担を減らし、前向きにルート営業に専念できる環境を作っていきましょう。
BtoB ECサイトでルート営業を効率化した成功事例
実際にBtoB ECサイト「アラジンEC」を利用した、ルート営業の効率化事例をご紹介します。シーマン株式会社様(医療機器販売)

カテーテル・チューブ・医療用のシステムや消耗品などを、循環器内科、放射線科など幅広い分野の病院へ販売しているシーマン様では、ルート営業先の病院でタブレットを活用することで、アラジンECを通じてすぐにサンプル発注や在庫確認ができるようになりました。
営業担当者が「アラジンEC」に発注データや補足コメントを入力すれば、そのまま基幹システムの「アラジンオフィス」にも取り込まれる仕組みです。営業担当者が帰社後にメール発注したり、事務担当者がシステムに入力したりする必要がなくなり、ミスも削減されました。病院への対応が素早くなり、サービスレベルの向上につながったのです。
さらに、メーカー1社に対して30分もかかっていた見積作成も、アラジンECの導入により10分で完了するようになりました。営業担当者がECサイトで欲しい商品をカートに入れていくようなイメージで、見積依頼する商品にチェックを入れていく仕組みにより大幅に効率化されています。
シーマン様の事例紹介ページはこちら!

このようにBtoB ECをルート営業に活用することにより、事務作業が大幅に削減され、効率化が図れます。社内に持ち帰って再度訪問するといった手間も減り、無駄な移動時間やコストもなくなるでしょう。リモートワーク、在宅勤務での対応もしやすくなります。
ルート営業を効率化する手段として、BtoB ECサイトを活用してはいかがでしょうか。
ルート営業の受発注業務を見直せる、分かりやすい解説マンガはこちら!

松岡 憲二(マツオカ ケンジ)
ベンチャー系ECベンダーにてセールスプランナー、ECコンサルタント、事業責任者として十数年従事した後、株式会社アイルに入社。大規模ECサイトからASPカート利用のスタートアップサイトまで様々な種類のサイト構築を経験。BtoCとBtoB、両方のノウハウを併せ持つことが強み。
PICK UP
導入事例
導入されたお客様の具体的な課題や解決方法、導入後の成果など詳しくお話いただきました。
よくある課題
業種別
-

 アパレル・ファッション
アパレル・ファッション鞄(かばん)、靴(くつ)、スポーツ用品、
肌着、制服・ユニフォーム、靴下、帽子など -

 食品・飲料・
食品・飲料・
酒類食料品全般、業務用食品、製菓、飲料、酒、
ワイン、介護食品、調味料など -

 理美容品
理美容品ヘアケア、カラー剤、エステ器具、ネイル用品、
ボディケアなど -

 建築資材・
建築資材・
住宅設備床材、外装資材など
-

 日用品・
日用品・
介護用品衛生用品、生活雑貨
など -

 工業製品・
工業製品・
電子部品電子部品、機械製造
など -

 OAサプライ品
OAサプライ品文具、事務用品など
-

 医療機器
医療機器歯科機器、検査機など
-

 化粧品
化粧品コスメ、口紅、香水
など -

 インテリア・
インテリア・
家具照明、収納家具など
-

 スポーツ用品
スポーツ用品シューズ、ウェアなど
-

 アクセサリー
アクセサリーピアス、指輪など
-

 ブランド向け
ブランド向け
展示会オンライン展示会
システム

[受付時間]10:00〜12:00 / 13:00〜17:30(土日祝除く)
 お問合せフォーム
お問合せフォーム
お役立ち情報|BtoB EC・Web受発注システム「アラジンEC」
5000社以上のBtoBノウハウで企業間の受発注業務に特化した貴社専用のECを構築することが可能です。受発注業務の効率化・コスト削減・販売促進など様々なシーンでご利用いただけるBtoB ECサイト構築・Web受発注システムです。