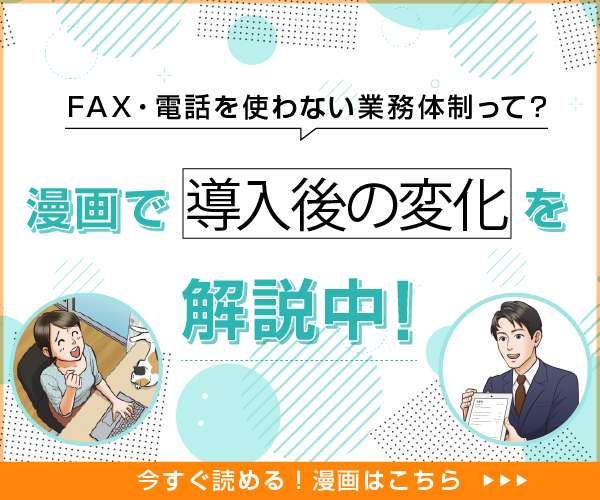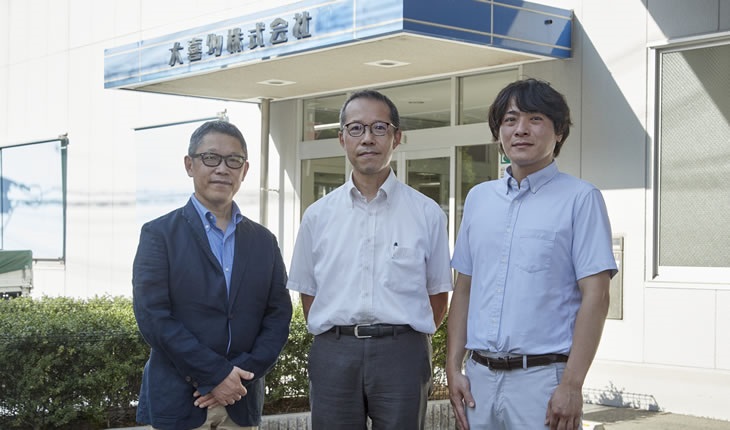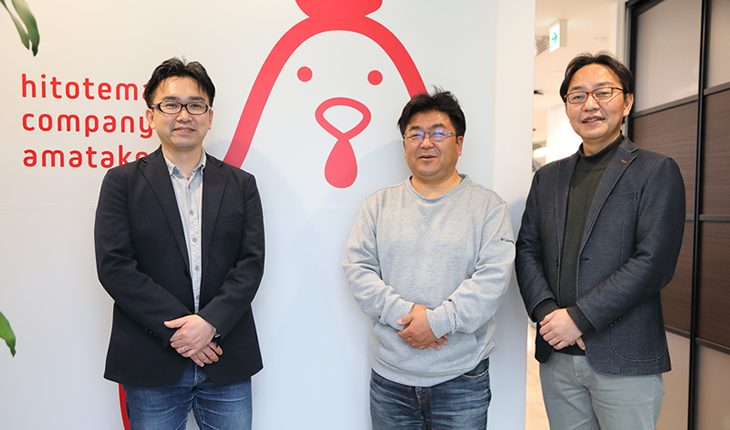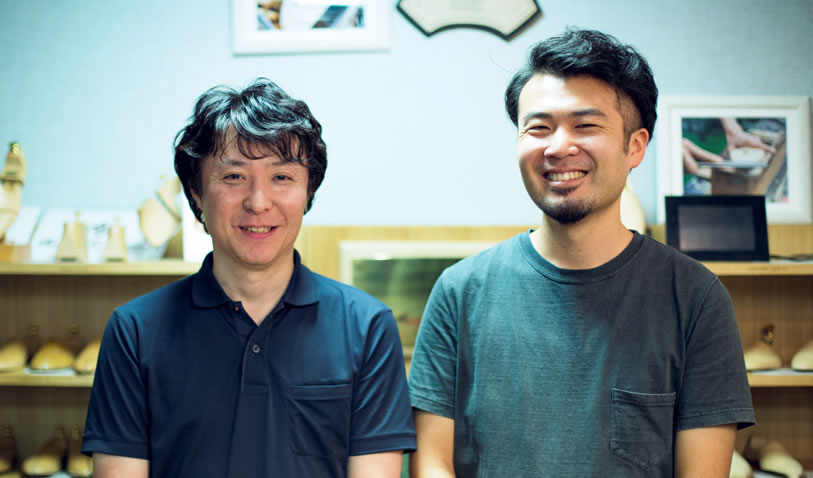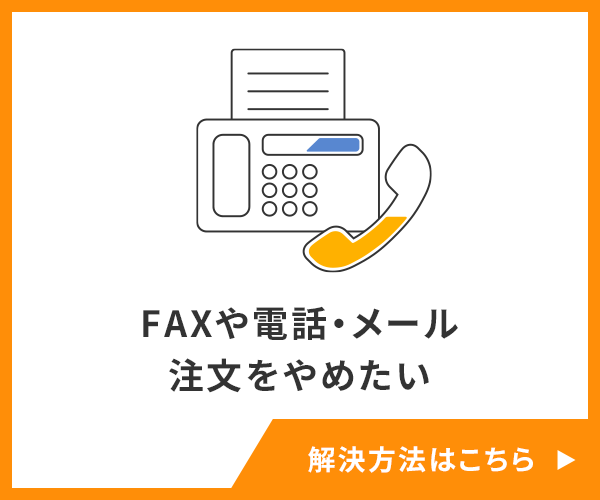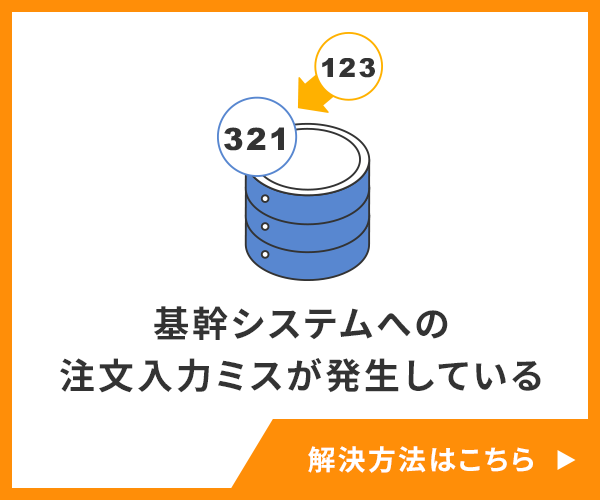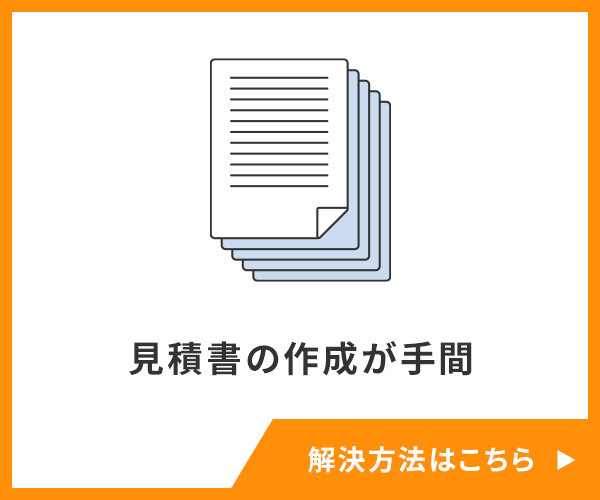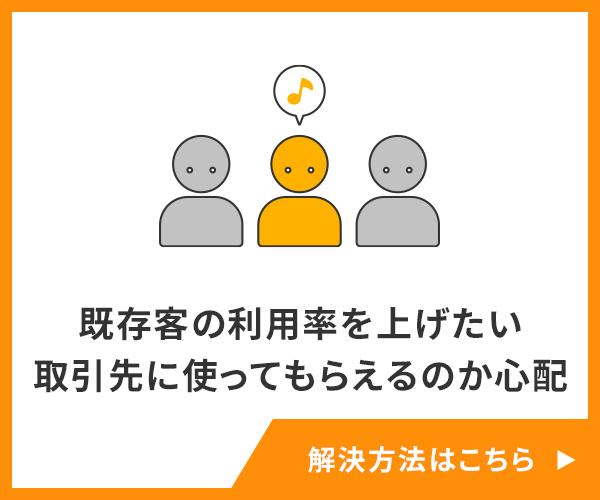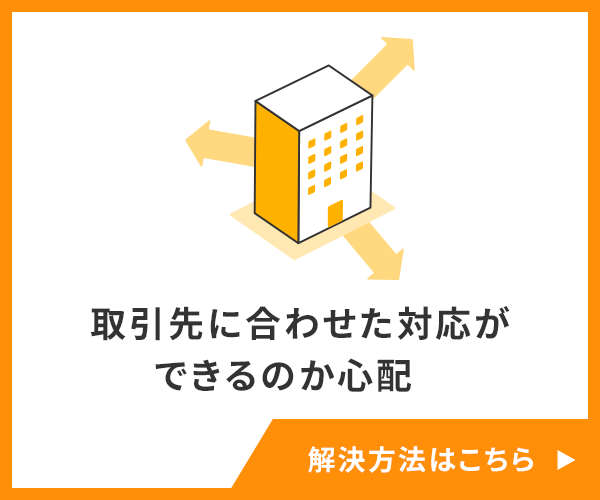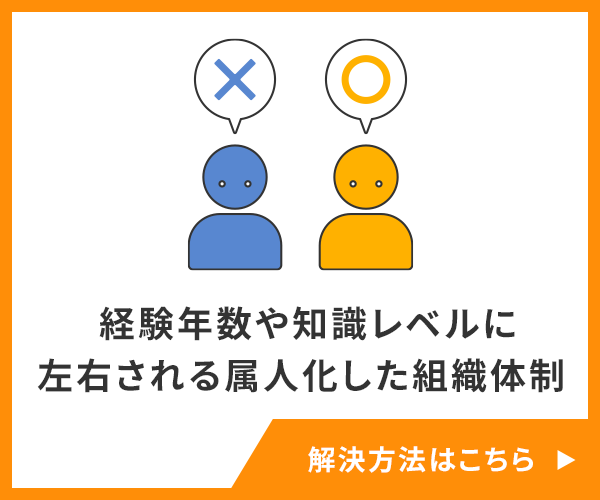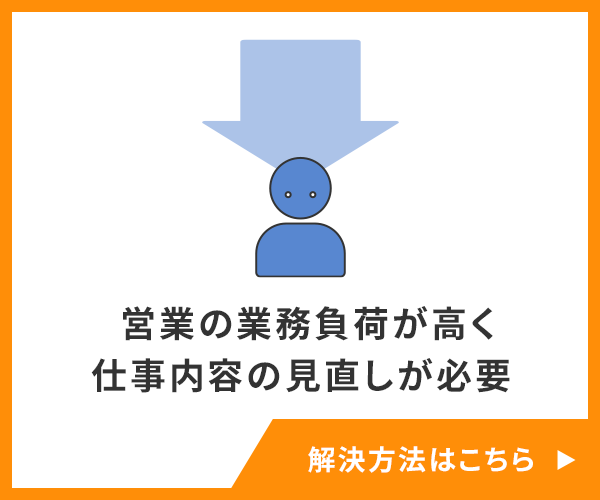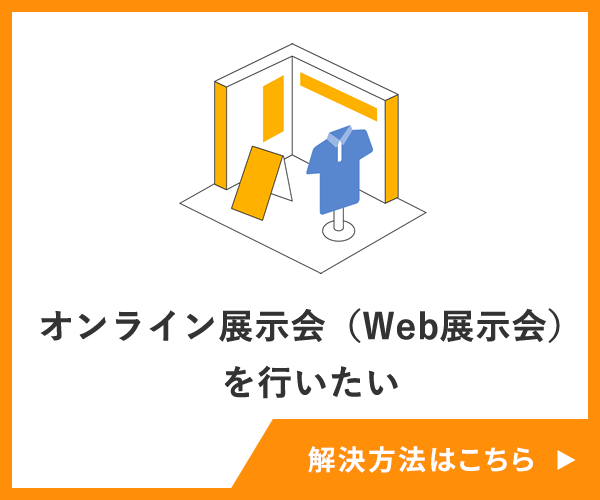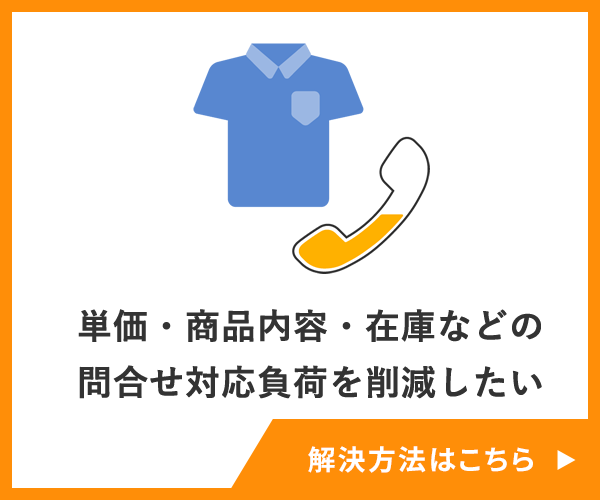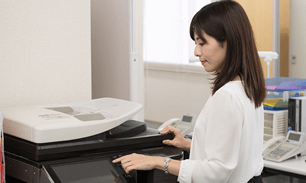お役立ち情報
Information
アイルが提供するお役立ち情報

デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの違いと関係性を解説

DXと深い関係を持つ言葉として「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」という言葉があります。あなたがDXだと思っているのは、実はデジタイゼーションやデジタライゼーションにすぎないかもしれません。
DXの前段階にデジタイゼーションやデジタライゼーションが位置しているため、それぞれの意味を正しく理解していないといつまでもDXの本質へたどり着かない可能性があります。
そこで今回は、デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの基礎的な知識を解説したうえで、具体的な例やメリット、成功のポイントまでご紹介します。DX推進を検討する中で、デジタイゼーションとデジタライゼーションの違いを知りたいと思っているビジネスパーソンの方は、ぜひ参考になさってください。


デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの違いとは
デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXにはさまざまな定義がありますが、それぞれデジタル化する「対象」が異なり、デジタイゼーション→デジタライゼーション→DXの3ステップで進めるのが一般的です。
以下では、それぞれの意味・例・メリットについて解説します。
デジタイゼーションとは

デジタイゼーション(Digitization)とは「情報」のデジタル化で、アナログ情報をデジタルデータに変換することを意味します。具体的には、情報をコンピューター処理するために数字の0と1の羅列に変換、つまり2進法に変換します。
総務省では、デジタイゼーションを「既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換すること」と定義しています。
身近な例
一般的なデジタイゼーションの例は、紙や書類をスキャンしてPDF化したり、画像化したりすることです。
ビデオテープ・DVDなどの映像メディアであれば、映像データファイル(MP4、MOVなど)に変換することがデジタイゼーションにあたります。
ビジネスでの例
これまで紙で発行していた書類をPDFデータなどで発行したり、紙のカタログ冊子をスキャンしてデータ化したりするサービスがよく見られます。
書面や口頭で行っていた連絡をメールやチャットなどの電子的なやり取りに切り替えることも、デジタイゼーションの一環です。

デジタイゼーションのメリット
デジタイゼーションのメリットはデータの保管、共有、検索、分析が容易になることです。データの作成・取り扱いにかける工数と費用を削減できます。
また、会議や商談のオンライン化であれば、時間とコストを削減しつつ、ハードルを下げてより多くの機会創出へつなげられることがメリットです。
デジタライゼーションとは

デジタライゼーション(Digitalization)では、「ビジネスプロセス」をデジタル化します。総務省では、デジタライゼーションを「組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること」と定義しています。
デジタイゼーションでデジタル化されたデジタルデータを用い、ビジネスプロセスの最適化やイノベーションの促進を実施します。
身近な例
デジタライゼーションとしてイメージしやすいのは、電子書籍の販売です。デジタイゼーションで書籍をデジタル化し、そのデータを販売してビジネスに生かすというモデルです。
動画共有プラットフォームもデジタライゼーションの一例です。娯楽目的や情報収集などを目的とした視聴用途と、個人や企業が制作した動画をアップロードする投稿用途の2種類に活用できます。
ビジネスでの例
コロナ禍を経て、電子承認や電子契約で取引をオンライン化し、プロセスを変化させるデジタライゼーションに取り組む企業が増えました。
紙の書類をFAXして発注していたのをPDFのメール送付に切り替えたり、Web受発注システムを利用する方法に切り替えたりして「受発注業務のデジタル化」をすることもデジタライゼーションの一例です。
ほかにも、これまで紙冊子で発行していた商品カタログをデジタルカタログの発行に切り替え、営業をオンライン化するなどのビジネス例があります。

デジタライゼーションのメリット
デジタライゼーションのメリットは、利便性を上げて効率化することにより、顧客との関係や業務効率を向上させる点です。
結果として取引が活発化したり、新規顧客開拓につながったりして、売上アップに貢献する例も多く見られます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
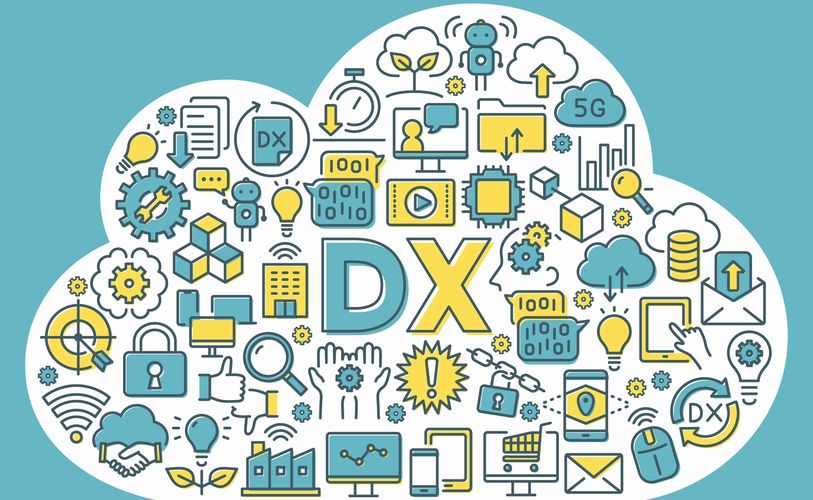
総務省では、DX(デジタルトランスフォーメーション/Digital Transformation)を「企業が外部エコシステム(顧客、市場)の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。
DXにより、ビジネスモデルをデジタル化し、デジタル技術を活用してビジネスモデルやサービスを変革・創造することができます。

身近な例
DXの例として、電子書籍のレンタルや読み放題サービス、映画やオリジナルコンテンツを配信する動画配信サービスなどが登場し、一般に定着していることが挙げられます。いずれも従来の買い切り型ではなくサブスクリプションサービスとして提供されており、ユーザーは気軽に利用しやすい反面、継続利用率も高く、サービス提供側としては長期的に着実な売り上げが期待できることなどがメリットです
電子書籍や動画配信の市場規模は、右肩上がりで増加を続けています。
ビジネスでの例
業務上の活用例として、電子受発注システムを導入し、見積・発注・問合せなどのやり取りをすべて電子化・自動化してデジタライゼーションを行ったうえで、効率化や顧客・従業員満足度の向上をはじめ、新たな働き方への変革や、企業価値の創出などを図るためのDXにつなげる企業も少なくありません。

ほかにもデジタルカタログの内容をECサイトへ移行し新たな販路を作り、売上増につなげているケースもあります。

DX推進のメリット
「守りのDX」とも言われる業務におけるDXは、効率化して業務時間を短縮することでワークライフバランスを整えたり、他の業務に充てる時間を増やしてイノベーションの創出・新規事業創出・競争力を高めたりするのがメリットです。
「一方で「攻めのDX」と言わるような対顧客のサービスを向上させるDXであれば、満足度が上がって売上アップに貢献します。サブスクリプション型サービスであれば、売上を安定させつつ、顧客データに合わせたサービス提案をするなどのビジネスモデルに発展させられます。

デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの関係性
改めて、混同しやすいデジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの関係性について解説します。
デジタイゼーションとデジタライゼーションの違い
デジタイゼーションとデジタライゼーションの元の語は「digitize」と「digitalize」です。「digitize」と「digitalize」はどちらも「デジタル化する」と訳されますが、元となっている名詞が異なります。
デジタイゼーションの語源である「digitize」の本質的意味は「デジタル信号化する・計数化する」で、デジタライゼーションの語源となっている「digitalize」は「digital」の動詞であり、「デジタル化する」という意味です。
結果的に、デジタイゼーションは「情報のデジタル化」を、デジタライゼーションは「ビジネスプロセスのデジタル化」を示すようになりました。
デジタライゼーションとDXの違い
上記で解説したとおり、デジタライゼーションは「ビジネスプロセスをデジタル化すること」であり、DXは「デジタル化によって新たな価値を創出し、ビジネスモデルや企業のあり方を変革していくこと」です。
DXは、攻めのDXと守りのDXに分けられます。
攻めのDXはステークホルダーに向けた改革で、ビジネスモデルを変えたり、新しい価値やイノベーション創出を行ったりします。既存サービスの質を向上させたり、新規サービスを考案したりすることを指します。
守りのDXは自社に向けた改革で、業務効率化や働きやすい職場づくり、ワークライフバランスの考慮などを行います。具体的には、業務プロセスを洗い出して再設計したり、データを可視化して最適な意志決定に生かしたりします。そのため、DXの手段として、ビジネスプロセスをデジタル化するデジタライゼーションが行われるケースが多く見られます。
3つの関係性=DX実現のためにデジタイゼーション・デジタライゼーションが必要
デジタイゼーションはDXの手段であり第一歩になりますが、デジタイゼーションだけではあまり意味をなしません。というのも、デジタイゼーションはあくまで「情報のデジタル化」であり、それだけではビジネスにとってプラスになるとは言い切れないからです。
きちんと成果を出すためには、最終的にどのような変革を目指すのか、DXへの道筋を立てた上でデジタイゼーション、デジタライゼーションを進めることが理想的です。目的と道筋が明確になっていれば、それに合わせて最適なデジタイゼーション、デジタライゼーションを選択し、実行に移すことができます。
DXやデジタライゼーションを成功させるコツ

いきなり全社的な変革を目指すのはハードルが高く、コストや時間がかかるため負担が大きくなります。DXやデジタライゼーションの対象となる業務を洗い出し、できるだけ小さい業務から順番に進めるのが良いでしょう。
また、無理なく着実にDXを進めるには、外部リソースを上手に使うことが大切です。社内のIT人材が不足している場合には、ITベンダーやSIer(システムインテグレーター)と協力しながら実現するのがおすすめです。DXやデジタライゼーションに関する専門知識を持っているベンダーやSIerの手を借りることで、自社に合った最適な進め方の提案や、適切なサポートを受けることができます。
受発注業務のDXに寄与するBtoB EC・Web受発注システム「アラジンEC」ではサポートに万全を期すため、企業様ごとに専用のチームを組んで対応する担当制を導入しています。
担当営業だけが対応する場合、問合せた際に担当営業が不在だと折り返しを待たねばならず、急なトラブルに対応できなかったり、対応レベルにばらつきが生まれたりするリスクがあります。システム担当や営業担当、サポート担当がチームとなりサポートを行うことで、このようなリスクや不安感の解消に努めています。

単なるデジタライゼーションで終わらせず、DXの実践へ
DX推進などのIT戦略を立てるには、デジタイゼーション、デジタライゼーション、DXを一連の流れで取り組むことが非常に重要です。それぞれの内容や立ち位置を理解し、優先順位を決めて取り組むことで、スムーズに計画から実践につなげられます。

ITベンダーと協力して進める場合、システムの提供を受ける段階、つまりデジタライゼーションまでの支援で終わるケースが多い傾向があります。BtoB EC・Web受発注システム「アラジンEC」と販売・在庫・生産管理システム「アラジンオフィス」を提供するアイルでは、システムの提供のみにとどまらず、その後の活用、つまりDXの実践段階まで支援を行っています。
導入前に課題をヒアリングし、システム導入後も専任のチームが課題解決に対して能動的に状況のヒアリングを実施。まるで専任コンサルタントかのように伴走しながら、貴社のDX推進を支援いたします。
DX推進の一環としてBtoB EC・Web受発注システムの導入をご検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

松岡 憲二(マツオカ ケンジ)
ベンチャー系ECベンダーにてセールスプランナー、ECコンサルタント、事業責任者として十数年従事した後、株式会社アイルに入社。大規模ECサイトからASPカート利用のスタートアップサイトまで様々な種類のサイト構築を経験。BtoCとBtoB、両方のノウハウを併せ持つことが強み。
PICK UP
導入事例
導入されたお客様の具体的な課題や解決方法、導入後の成果など詳しくお話いただきました。
よくある課題
業種別
-

 アパレル・ファッション
アパレル・ファッション鞄(かばん)、靴(くつ)、スポーツ用品、
肌着、制服・ユニフォーム、靴下、帽子など -

 食品・飲料・
食品・飲料・
酒類食料品全般、業務用食品、製菓、飲料、酒、
ワイン、介護食品、調味料など -

 理美容品
理美容品ヘアケア、カラー剤、エステ器具、ネイル用品、
ボディケアなど -

 建築資材・
建築資材・
住宅設備床材、外装資材など
-

 日用品・
日用品・
介護用品衛生用品、生活雑貨
など -

 工業製品・
工業製品・
電子部品電子部品、機械製造
など -

 OAサプライ品
OAサプライ品文具、事務用品など
-

 医療機器
医療機器歯科機器、検査機など
-

 化粧品
化粧品コスメ、口紅、香水
など -

 インテリア・
インテリア・
家具照明、収納家具など
-

 スポーツ用品
スポーツ用品シューズ、ウェアなど
-

 アクセサリー
アクセサリーピアス、指輪など
-

 ブランド向け
ブランド向け
展示会オンライン展示会
システム

[受付時間]10:00〜12:00 / 13:00〜17:30(土日祝除く)
 お問合せフォーム
お問合せフォーム
お役立ち情報|BtoB EC・Web受発注システム「アラジンEC」
5000社以上のBtoBノウハウで企業間の受発注業務に特化した貴社専用のECを構築することが可能です。受発注業務の効率化・コスト削減・販売促進など様々なシーンでご利用いただけるBtoB ECサイト構築・Web受発注システムです。